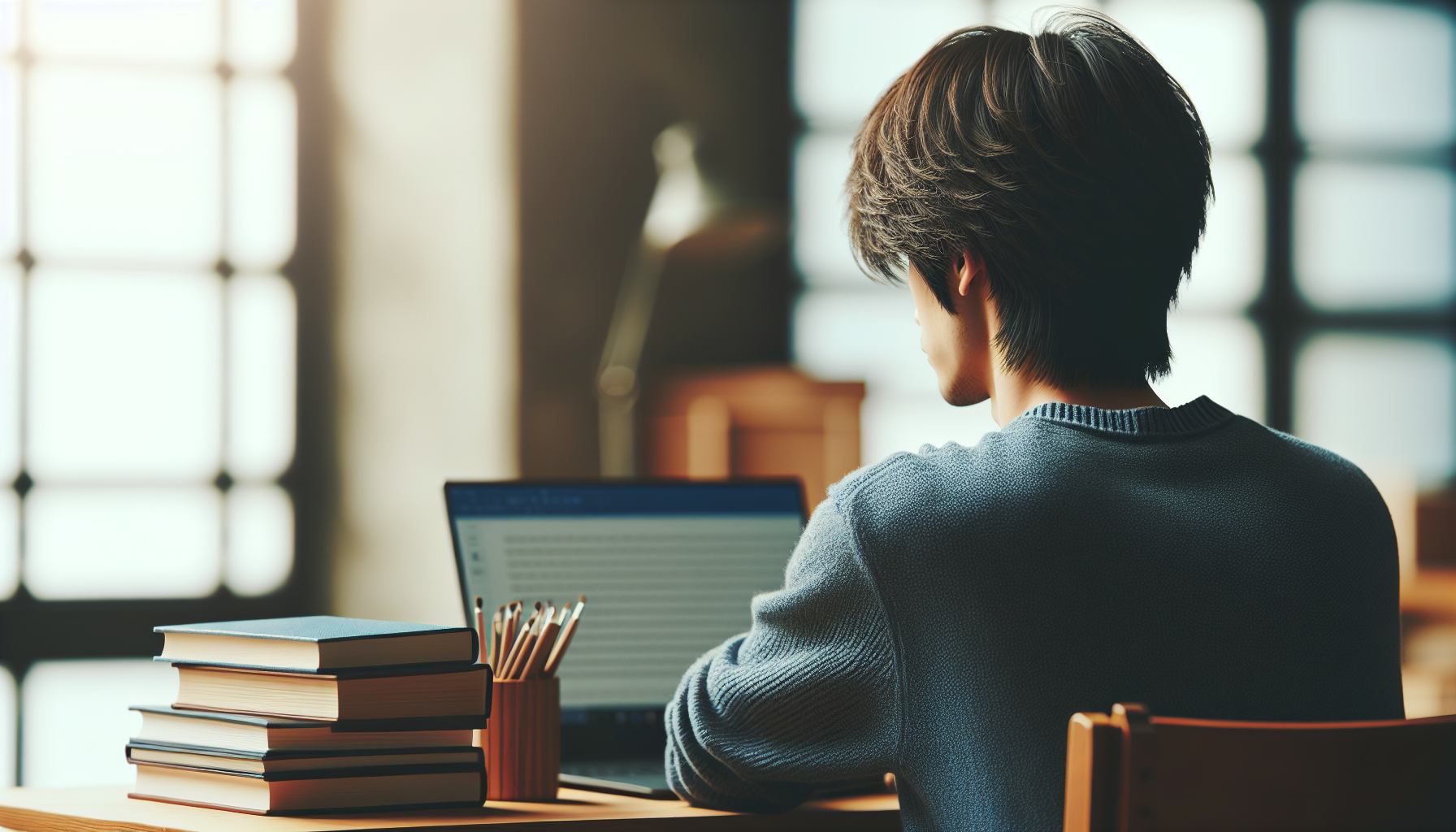通信制大学で学びたいけれど、「学費の負担が大きくて、奨学金が使えるか心配…」や「何か知らないと損するような裏ワザはないのかな?」と考えている方もいるでしょう。
実は、通信制大学でも利用できる奨学金制度は多く、情報を知っているかどうかで経済的な負担は大きく変わってきます。
この記事では、通信制大学で学びながら、奨学金を上手に活用したいと考えている方に向けて、
– 通信制大学で申し込める奨学金の種類と条件
– 知らないと損する奨学金活用の裏ワザ
– 奨学金申請で失敗しないための注意点
上記について、解説しています。
経済的な心配事を少しでも減らして、学びたいことに集中できる環境はとても大切です。
この記事を読めば、自分に合った奨学金を見つけ、賢く活用するための具体的な方法がわかりますので、ぜひ参考にしてください。
通信制大学で利用できる奨学金制度
通信制大学でも、通学制の大学と同じように様々な奨学金制度を活用できることをご存知でしたか。
「働きながら学びたいけれど、学費の負担が心配…」と感じている方も、経済的な理由で学びを諦める必要はありません。
あなたの状況に合った奨学金が見つかる可能性は十分にあります。
通信制大学は学費が比較的安いことから、奨学金の対象外だと思い込んでいる方も少なくないでしょう。
しかし、日本学生支援機構(JASSO)をはじめ、多くの機関が通信教育課程で学ぶ学生も支援の対象としているのです。
学びたいという意欲を経済的な面からサポートしてくれる制度は、あなたが思う以上に充実しています。
具体的には、最も代表的な日本学生支援機構(JASSO)の奨学金が挙げられます。
これには返済不要の「給付型」と、卒業後に返済する「貸与型」の2種類が存在。
さらに、大学が独自に設けている成績優秀者向けの特待生制度や、特定の地域に住む学生を対象とした地方自治体の奨学金など、選択肢は実に多彩です。
日本学生支援機構の奨学金を活用しよう
通信制大学で学ぶ際、最も心強い味方となるのが日本学生支援機構(JASSO)の奨学金制度です。
この公的な制度は、経済的理由で修学が困難な学生を支えるもので、通信教育課程の学生ももちろん対象となります。
奨学金には、返済不要の「給付型奨学金」と、卒業後に返済する「貸与型奨学金」の2つのタイプが存在します。
貸与型はさらに、無利子の「第一種奨学金」と、有利子の「第二種奨学金」に分かれているのです。
特に第二種奨学金は、比較的多くの人が利用でき、月額2万円から12万円の範囲で、自身の学習計画に合わせて1万円単位で希望額を選択できます。
採用には学力基準と家計基準がありますが、まずはJASSOの公式サイトで進学資金シミュレーターを試してみるのがよいでしょう。
計画的な学習と生活のために、この制度を最大限活用してください。
地方公共団体や民間団体の奨学金を検討
日本学生支援機構(JASSO)以外にも、地方公共団体や民間団体が提供する奨学金は有力な選択肢となります。
お住まいの都道府県や市区町村が独自に設けている奨学金制度は、見逃せない存在でしょう。
例えば、東京都育英資金のように、その地域に居住している学生を対象とした制度が見つかります。
これらは返済不要の給付型も多く、学費負担を大きく軽減するのに役立ちます。
まずは、自治体のホームページで情報を確認することが第一歩です。
また、企業や公益財団法人が運営する民間団体の奨学金も非常に魅力的。
あしなが育英会や交通遺児育英会のように特定の境遇にある学生を支援するものから、特定の専門分野を志す学生を対象とするものまで多岐にわたります。
これらは返済義務のない給付型が多いため、積極的に活用したいところ。
ただし、募集期間が短く採用枠も限られる場合がほとんどなので、大学の学生課などで常に最新情報をチェックし、早めに行動することが重要になります。
大学独自の奨学金制度の魅力
多くの通信制大学では、学生の経済的負担を軽くするために独自の奨学金制度を用意しています。
その最大の魅力は、返済が不要な「給付型」奨学金や、授業料の一部が免除される「学費減免制度」が充実している点にあるでしょう。
例えば、サイバー大学の独自の給付型奨学金や、産業能率大学の同窓会奨学金など、各大学が特色ある支援を行っているのです。
これらの制度は、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金との併用が可能なケースも多く、経済的な不安を大きく和らげてくれます。
また、成績優秀者や特定の資格保有者を対象とした奨学金もあり、選考基準が大学独自であるためJASSOの基準に合わなくても採用されるチャンスが生まれます。
入学を検討している大学の公式サイトで、どのような支援があるのか必ず確認しましょう。
奨学金返済を軽減する裏ワザ
通信制大学で借りた奨学金の返済に、不安を感じている方もいるかもしれません。
しかし、毎月の返済額を減らしたり、一時的に支払いを待ってもらえたりする公的な制度が存在します。
これらを「裏ワザ」として知っておくことで、返済の負担を大きく軽減させることが可能です。
なぜなら、これらの制度は、経済的な事情でキャリアアップや学びを諦めることがないように設けられた、一種のセーフティーネットだからでしょう。
特に、働きながら学ぶことが多い通信制大学の学生は、収入が変動しやすい状況も考えられます。
そのような万が一の事態に備えて、無理なく返済を続けられるよう支援する目的があるのです。
具体的には、日本学生支援機構(JASSO)の「減額返還制度」が挙げられます。
この制度は、経済的な困難といった事情がある場合に、一定期間、毎月の返済額を2分の1または3分の1に減らせる仕組みです。
また、「返還期限猶予制度」では、同様の理由で最長10年間、返済自体を待ってもらうこともできます。
減額返還制度で支払い負担を減らす
奨学金の返済が経済的に厳しいと感じたら、日本学生支援機構が提供する「減額返還制度」を賢く活用しましょう。
この制度を利用すれば、毎月の返済額を一時的に2分の1、あるいは3分の1まで減額してもらえます。
もちろん、これは返済総額が減るわけではなく、減額した分だけ返済期間が長くなる仕組みである点は理解しておかなければいけません。
災害や失業、経済的な理由が対象となり、給与所得者であれば年収325万円以下といった収入基準を満たす必要があります。
1回の申請で12ヶ月間適用され、通算で最長15年(180ヶ月)まで延長が認められるので、生活再建の大きな助けになるでしょう。
申請はインターネットの「スカラネット・パーソナル」から手軽にできるため、まずは公式サイトで詳細を確認してみてください。
返還期限猶予制度の利用方法
病気や失業、経済的な事情で奨学金の返済が困難になった際に活用できるのが、返還期限猶予制度です。
これは一定期間、返済そのものを待ってもらう制度で、例えば給与所得者の年間収入が300万円以下といった経済困難の基準を満たす場合に利用できます。
申請は原則として1年ごとに必要となり、日本学生支援機構のWebサービス「スカラネット・パーソナル」を通じて行いましょう。
「奨学金返還期限猶予願」と状況を証明する書類を提出することで、最長で通算10年(120か月)まで返済の猶予が認められる可能性があります。
ただし、これはあくまで返済を先延ばしにする措置であり、返済総額が減るわけではありません。
返済が厳しいと感じたら、延滞してしまう前にこの制度の利用を検討することが重要です。
在学猶予制度で返済を先延ばし
すでに奨学金を返済中の社会人の方が通信制大学へ入学する場合、「在学猶予」という制度を活用すれば返済を一時的にストップできます。
これは日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を利用している人が対象で、在学証明書を提出することで、在学期間中の返済が猶予される仕組みとなっています。
例えば、4年制の通信制大学に在籍するなら、最長で4年間は返済を待ってもらえるでしょう。
手続きは非常に簡単で、インターネットサービスの「スカラネット・パーソナル」から在学届を提出するだけ。
この制度を使えば、在学中は学費の支払いや学業に集中できるため、経済的な負担を大きく軽減する有効な裏ワザといえるでしょう。
ただし、あくまで返済の先延ばしであり、返済額自体が免除されるわけではない点には注意が必要です。
卒業後の生活を見据え、計画的に活用することが大切になります。
奨学金返済の注意点とリスク
奨学金は学びを支える心強い制度ですが、本質的には「借金」であることを忘れてはいけません。
卒業後の返済計画を具体的に立てずに利用してしまうと、将来のあなたの生活を圧迫する大きなリスクとなり得ます。
通信制大学で学びながら、ご自身の将来設計と照らし合わせて慎重に検討することが何よりも大切でしょう。
なぜなら、奨学金の返済は卒業後から始まり、場合によっては数十年にわたって続く長期的な義務となるからです。
卒業後の収入が不安定だったり、結婚や出産といったライフイベントで予期せぬ出費が重なったりすると、返済が困難になるケースも少なくありません。
「自分は大丈夫」と思っていても、将来の不確実性を考慮し、リスクを事前に把握しておくべきなのです。
具体的には、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を3ヶ月以上延滞した場合、個人信用情報機関にその情報が登録されてしまいます。
そうなると、クレジットカードの新規作成や、自動車・住宅ローンの契約が非常に難しくなる可能性があります。
軽い気持ちで利用した奨学金が、あなたの将来の信用に傷をつける事態は避けたいものです。
返済義務は消えないことを理解する
奨学金の返済を支援する減額返還や猶予制度は心強い味方ですが、これらはあくまで一時的な措置に過ぎません。
最も重要なのは、奨学金の返済義務は決して消滅しないという事実を理解しておくこと。
これは、通信制大学で学ぶ皆さんも例外ではないのです。
例えば、日本学生支援機構(JASSO)から借り入れた場合、返済総額が減るわけではなく、完済までその義務は続きます。
自己破産をしても、保証人や連帯保証人に請求が移行するケースがほとんどでしょう。
もし返済を3ヶ月以上延滞すると、年率3%(令和6年3月までに採用された利率)の延滞金に加え、個人信用情報機関に事故情報として登録されます。
これにより、将来のローン契約やクレジットカード作成が著しく困難になるため、安易に考えず、卒業後を見据えた計画的な利用を心がけてください。
返済金額に変化はないが計画的に
減額返還制度や返還期限猶予制度は、月々の経済的負担を一時的に軽くしてくれる非常に心強い味方です。
しかし、これらの制度を利用しても、奨学金の返済総額そのものが減額されるわけではない点を理解しておかなければなりません。
あくまで支払いを先延ばしにするか、月々の返済額を調整する措置であり、最終的に支払うべき元金と利息に変わりはないのです。
特に、利息が加算される第二種奨学金の場合、返済期間が長引くことで支払う利息の総額が増えてしまう可能性も出てくるでしょう。
そのため、これらの制度は緊急避難的な対策と捉え、将来の収入増や家計の見直しといった長期的な視点で返済計画を立て直すことが不可欠となります。
安易な利用に頼るのではなく、猶予期間を自己投資の機会と捉えるなど、計画的に将来へ備える姿勢が求められます。
法律改定による制度変更の可能性
奨学金制度は国の法律に基づいて運営されているため、将来的な法改正によって内容が変更される可能性がある点を理解しておく必要があります。
例えば、2020年度から始まった「高等教育の修学支援新制度」のように、給付型奨学金の対象者が拡大されたり、授業料減免制度が導入されたりするケースがありました。
このように、制度変更は利用者にとって有利に働くこともあれば、金利の見直しや保証制度の変更など、返済計画に影響を及ぼす改定が行われる可能性も否定できません。
過去には所得に応じて返還額が変わる「所得連動返還方式」が導入されるなど、返済方法にも大きな変化が見られます。
したがって、奨学金を利用する際は、契約時の内容だけでなく、日本学生支援機構(JASSO)の公式サイトなどで常に最新の情報を確認し、社会情勢の変化にも注意を払う姿勢が大切になるでしょう。
通信制大学での学費節約術
通信制大学の学費は比較的安価ですが、奨学金以外にも費用を節約するテクニックが存在します。
教材の揃え方を見直したり、利用できる税金の控除制度を調べたりすることで、経済的な負担をさらに軽くすることが可能です。
少しの工夫が、あなたの学びを力強く後押ししてくれるでしょう。
なぜなら、学費総額の中で意外と大きな割合を占めるのが、テキスト代などの教材費だからです。
また、働きながら学ぶ社会人学生が多い通信制大学だからこそ、活用できる公的な支援制度も整備されています。
こうした見落としがちなポイントに目を向けるだけで、年間で数万円単位の節約につながることも少なくありません。
例えば、指定された教科書は新品にこだわらず、メルカリや古本屋で探してみるのがおすすめです。
前の期の学生が出品した、書き込みの少ない綺麗な教科書が定価の半額以下で手に入ることもあります。
また、社会人学生の場合は、学費が所得控除の対象となる「特定支出控除」という制度を利用できる可能性もあるため、一度確認してみる価値は十分にあるでしょう。
教育訓練給付金の活用法
通信制大学の学費を抑える強力な味方となるのが、厚生労働省の「教育訓練給付金」制度です。
これは雇用保険に加入している、または加入していた社会人が利用できるもので、学び直しを金銭的に支援してくれます。
特に注目すべきは「専門実践教育訓練」で、対象講座に指定されていれば、支払った学費の最大70%、年間で上限56万円もの給付を受けられることもあります。
利用するには、まずご自身が希望する大学の講座が対象になっているかを確認しましょう。
その上で、受講開始の1ヶ月前までを目安に、ハローワークでキャリアコンサルティングを受け、支給申請手続きを行う必要があります。
奨学金とは別に活用できるため、学費負担を劇的に軽減できる非常に有効な裏ワザといえるでしょう。
教育ローンを賢く利用する方法
奨学金だけでは学費が不足する場合、教育ローンの活用も有効な選択肢となります。
教育ローンには、日本政策金融公庫が扱う「国の教育ローン」と、銀行などの民間金融機関が提供するものの2種類が存在します。
国の教育ローン(教育一般貸付)は、年2.4%前後(2024年5月時点)の固定金利で、最高350万円まで借入れできるのが大きな魅力でしょう。
民間ローンに比べて金利が低く、返済計画が立てやすい特徴があります。
一方、民間金融機関のローンは変動金利が多いものの、キャンペーン金利でお得に利用できたり、審査がスピーディーだったりするメリットが考えられます。
賢く利用するためには、まず国の教育ローンを検討し、その上で複数の民間ローンを比較することが重要です。
各金融機関のウェブサイトで返済シミュレーションを行い、ご自身の状況に最も適したプランを見つけましょう。
奨学金との併用も可能なので、無理のない資金計画を立てることが大切です。
日常生活費を抑える裏ワザ
通信制大学での学習と両立させながら、日々の生活費を賢く抑える裏ワザがあります。
まず着手すべきは、毎月必ず発生する固定費の見直しでしょう。
特にスマートフォンの通信費は、大手キャリアからahamoやpovoといった月額3,000円以下の格安SIMへ乗り換えるだけで、年間で数万円単位の節約につながります。
次に大きな割合を占める食費は、自炊を基本とし、業務用スーパーなどを活用して食材を安く仕入れることが節約の鍵となります。
外食を月に2回減らすだけでも、5,000円程度の節約が可能かもしれません。
さらに、メルカリで不要品を売ったり、ポイントサイトでコツコツ貯めたりする「ポイ活」も、有効な手段です。
こうした小さな工夫の積み重ねが、無理なく続けられる節約術の基本となり、学業に集中できる環境を整えてくれるはずでしょう。
奨学金と通信制大学に関するQ&A
通信制大学での奨学金利用を考えると、「本当に自分は対象になるのだろうか」といった様々な疑問や不安が浮かんでくるかもしれませんね。
通学制とは異なる学習スタイルだからこそ、心配になる方もいるでしょう。
このセクションでは、そのようなあなたの悩みを解消するため、奨学金と通信制大学に関するよくある質問にQ&A形式で詳しくお答えしていきます。
通信制大学には、働きながら学ぶ社会人学生が多いなど、通学制とは異なる学習環境があります。
そのため、奨学金の申込条件や審査基準、利用できる範囲について、独自の疑問が生まれやすい傾向にあるのです。
特に、収入の扱いやスクーリングにかかる費用など、通信制ならではのポイントでつまずいてしまうケースは少なくありませんでした。
具体的には、「社会人学生でも日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を借りられるのか」「スクーリング時の交通費や宿泊費は奨学金の対象になるのか」といった、多くの方が気になる質問に回答。
また、「世帯収入の基準は通学制と違うのか」「休学した場合の手続きはどうなるのか」など、一歩踏み込んだ疑問も解消していきます。
奨学金の返済に困った時の相談先
奨学金の返済に行き詰まった場合、何よりも先に貸与元である日本学生支援機構(JASSO)の「奨学金相談センター」へ連絡することが解決への第一歩です。
延滞が始まる前に、月々の返済額を減らせる減額返還制度や、一時的に返済を待ってもらう返還期限猶予制度といった救済措置が利用できないか相談してみましょう。
電話で現在の収入状況や返済が難しい理由を具体的に伝えれば、専門の相談員があなたに合った制度や手続きの流れを丁寧に案内してくれます。
もし奨学金以外にも借金があり多重債務の状態なら、財務局の「多重債務相談窓口」や法的な解決を視野に入れるなら「法テラス(日本司法支援センター)」も有効な相談先になるでしょう。
決して一人で悩まず、できるだけ早い段階で公的な専門機関を頼ることが、問題を深刻化させないための最も賢明な選択といえます。
通信制大学の学費を抑える方法
通信制大学の学費は通学課程に比べて安価ですが、工夫次第でさらなる節約が可能です。
まず、高額になりがちなテキスト代は、新品ではなく中古品をメルカリなどで探したり、大学図書館を積極的に活用したりすることで費用を削減できます。
電子書籍版があれば、そちらを選ぶのも一つの手でしょう。
次に、スクーリング費用も見直すべきポイントになります。
遠方の会場は交通費や宿泊費がかさむため、オンラインスクーリングを最大限活用したり、近隣の会場を選んだりするのが賢明です。
また、多くの大学では、入学前に取得した資格(例:TOEIC、基本情報技術者試験)や他大学の単位を認定する制度を設けています。
これを活用すれば履修科目を減らせるので、結果的に学費を抑えることにつながるのです。
最も重要なのは、学習計画をしっかり立て、最短年数で卒業すること。
これが最大の節約術といえるかもしれません。
奨学金の猶予制度の詳細
奨学金の返済が困難になった際に役立つのが猶予制度で、これにはいくつかの種類が存在します。
通信制大学などに在学中であれば、「在学猶予」を申請することで返済を一時的にストップさせることが可能です。
手続きは、日本学生支援機構のWebサービス「スカラネット・パーソナル」から「在学届」を提出するだけで完了します。
一方、災害や傷病、あるいは失業などで経済的に返済が難しい状況に陥った場合には、「返還期限猶予」という制度を利用できるでしょう。
例えば、給与所得者の年間収入が300万円以下といった基準を満たせば、経済困難を理由に最長10年(通算)の猶予が認められます。
ただし、第二種奨学金では猶予期間中も利息は加算されるため、返済総額自体が減るわけではない点を理解しておく必要があります。
まとめ:通信制大学の奨学金を味方に、あなたの学びを応援します
今回は、通信制大学で学びたいけれど、学費のことで一歩踏み出せないと考えている方に向けて、- 通信制大学で利用できる奨学金の種類- 奨学金を最大限に活用するための方法- 申請する前に知っておきたい注意点上記について、解説してきました。
通信制大学であっても、奨学金制度を賢く利用すれば、経済的な負担を大きく減らせるでしょう。
様々な制度が用意されており、学びたい意欲さえあれば道は開けるのです。
金銭的な理由で学びを諦めかけていた方もいるかもしれません。
まずはこの記事で紹介した情報を参考に、ご自身が利用できる奨学金制度がないか調べてみましょう。
少しの行動が、未来を大きく変えるきっかけになります。
「学びたい」というあなたのその気持ちは、何よりも価値のあるものです。
奨学金は、その尊い一歩を力強く後押ししてくれる心強いサポーターでした。
諦める前に、まずは利用できる制度を一つひとつ確認してみてください。
あなたの挑戦を、筆者は心から応援しています。