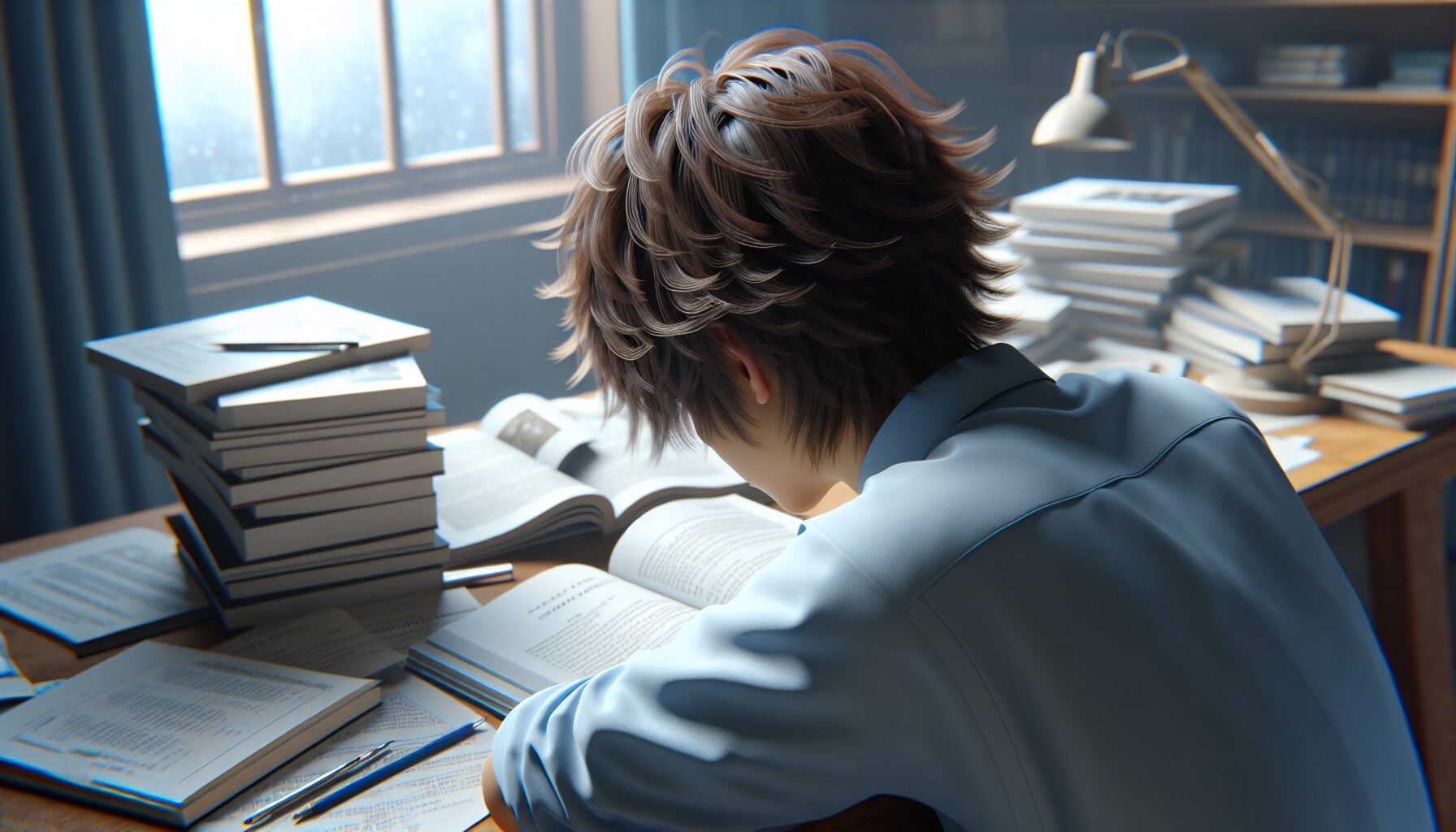都立入試が近づくにつれて、「理科の点数がなかなか上がらないけど大丈夫かな…」と不安に感じていませんか。
「入試まで時間がないのに、勉強が追いついていない…」と焦りを感じている方もいるでしょう。
しかし、諦めるのはまだ早いです。
実は、都立入試の理科には、ちょっとしたコツや考え方を知っているだけで得点に繋がりやすくなるポイントが存在するのです。
この記事では、都立入試の理科で、効率よく点数を伸ばしたいと考えている方に向けて、
– すぐに実践できる得点アップの裏ワザ
– 時間がない人でも間に合う効率的な勉強法
– 本番で焦らないための時間配分のコツ
上記について、解説しています。
理科が苦手な方でも、今日からすぐに試せる具体的な方法ばかりをまとめました。
この記事を読めば、本番で1点でも多く得点するためのヒントが見つかるはずでしょう。
ぜひ参考にしてください。
都立入試理科で得点を上げる理由
都立入試の理科は、実は合格をぐっと引き寄せるための戦略的な得点源となり得ます。
「覚えることが多くて苦手…」と感じ、対策を後回しにしている方もいるかもしれません。
しかし、理科は正しい方法で対策すれば、安定して高得点を狙える非常に重要な科目なのです。
その理由は、多くの受験生が国語・数学・英語の対策に時間を費やし、理科に十分な時間を割けていない現状があるからです。
周りの受験生が苦手としている科目だからこそ、あなたが少し努力するだけで大きな差をつけることが可能でしょう。
理科で稼いだ点数は、他の科目での少しのミスをカバーしてくれるだけでなく、精神的な余裕にも繋がりました。
例えば、都立入試の理科は出題傾向が比較的はっきりしています。
大問1では各分野の小問集合、大問の後半では実験や観察に関する思考力を問う問題が出されるなど、形式が定着しているのが特徴です。
そのため、出題されやすい分野や問題形式に的を絞って学習することで、効率的に得点を伸ばすことが十分に可能なのです。
ライバルとの差をつけるチャンス
都立高校入試において、多くの受験生は英語・数学・国語の主要3教科に学習時間の大部分を費やす傾向があります。
塾のカリキュラムもこの3教科が中心になることが多く、理科や社会の対策はどうしても手薄になりがちでしょう。
この状況こそが、あなたにとって大きなチャンスを生み出すのです。
ライバルと差がつきにくい理科で安定して高得点を獲得できれば、総合点で一気に優位に立てます。
実際に、理科の平均点は例年60点前後で推移しており、ここで80点以上を目指すことは決して不可能ではありません。
他の受験生が取りこぼす問題をあなたが確実に正解することで、合格ラインを大きく超えることも夢ではないでしょう。
理科は単なる暗記科目ではなく、合否を分ける重要な「戦略科目」だと考えてください。
暗記と理解のバランスが鍵
都立入試の理科で高得点を掴むには、知識の暗記と現象の理解、この二つのバランスが極めて重要になります。
例えば、大問1の小問集合では基本的な知識が問われますが、近年は単なる一問一答形式ではない問題も増えてきました。
化学式や「オームの法則」のような物理公式を覚えることは大前提ですが、それだけでは太刀打ちできません。
大切なのは、「なぜそうなるのか」という原理原則を深く掘り下げて考える力です。
例えば、植物の光合成の仕組みを覚えるだけでなく、光の強さや二酸化炭素濃度が光合成にどう影響するのか、その関係性をグラフから読み解く力が求められるでしょう。
丸暗記した知識を、実験の考察や計算問題で自在に活用する力こそが「理解」なのです。
この暗記と理解の両輪をバランス良く鍛えることで、初めて見るような応用問題にも対応できる真の実力が身につきます。
裏ワザで効率的に学ぶ重要性
都立入試の理科は、物理・化学・生物・地学という4つの広範な分野から出題されるため、全ての範囲を完璧にマスターするのは非常に困難といえます。
限られた受験勉強の時間の中で合格点を掴むためには、真正面から取り組むだけでなく、効率を重視した学習戦略が不可欠でしょう。
そこで重要になるのが、いわゆる「裏ワザ」の活用です。
裏ワザとは、単なる小手先のテクニックではありません。
過去の出題傾向を分析し、頻出するパターンや解法を最短で身につけるための合理的な学習法を指すのです。
例えば、大問1で出題される小問集合を確実に取るための知識整理や、計算を簡略化するテクニックもその一つ。
これらを活用すれば学習時間を大幅に短縮でき、その分、苦手分野の克服や演習に時間を割けるようになります。
時間を有効に使い、得点に直結する知識を優先的に学ぶことこそ、ライバルに差をつける鍵となるでしょう。
都立入試理科の出題傾向と重要テーマ
都立入試の理科は学習範囲が広く、どこから手をつければ良いか分からず、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
実は、都立理科には明確な出題傾向があり、頻出のテーマもほぼ決まっているのです。
この傾向をしっかり掴むことこそ、効率的な得点アップへの一番の近道です。
なぜなら、都立入試の理科は物理・化学・生物・地学の4分野から、ほぼ均等に大問が出題される形式が長年続いているからです。
これは、特定の分野だけを得意にしても高得点は狙えず、苦手分野を放置すると、それがそのまま失点に直結してしまうことを意味します。
全分野をバランス良く対策することが、合格点を勝ち取るための絶対条件と言えるでしょう。
この出題形式を理解した上で、さらに各分野で特に出題されやすい「重要テーマ」が存在します。
過去の出題傾向から頻出テーマを分析し、そこに絞って対策することで、学習の負担を減らしながら得点力を大きく伸ばすことが可能です。
以下で、各分野における重要テーマと具体的な対策法を詳しく解説していきます。
頻出分野ランキングをチェック
都立高校入試の理科で効率よく得点を稼ぐには、まず出題されやすい分野を知ることが不可欠でしょう。
理科は例年、物理・化学・生物・地学の4分野から大問が1つずつ、そして各分野の小問を集めた大問が1つの計5題構成となっています。
過去問を分析すると、特に頻出とされるテーマが見えてきます。
具体的には、化学の「化学変化とイオン」、物理の「電流とその利用」、生物の「植物のつくりと働き」、地学の「天体の動きと地球の自転・公転」は最優先で対策すべき単元です。
これらの分野は、大問の配点の約8割を占めることも珍しくありません。
令和5年度入試でもこの傾向は続いており、重点的に学習することで、全体の得点を大きく底上げすることが可能となります。
まずは過去問を一度解いてみて、これらの頻出分野から自分の苦手な箇所を洗い出す作業から始めてください。
よく出る公式と重要語句
都立入試の理科では、毎年同じような公式や重要語句が繰り返し出題される傾向にあります。
これらを確実に押さえることが、得点アップへの最短ルートになるでしょう。
物理分野なら、オームの法則「電圧(V)=抵抗(R)×電流(I)」は絶対に欠かせない公式です。
また、化学で頻出する質量パーセント濃度を求める式「(溶質の質量 ÷ 溶液の質量) × 100」も確実に暗記しておく必要があります。
生物分野では、消化酵素の名前と働きをセットで覚えることが重要になります。
例えば、「アミラーゼはデンプンを分解する」といった形で、具体的な働きと関連付けて記憶しましょう。
地学分野においては、地層の年代を特定する「示準化石」と、当時の環境を示す「示相化石」の違いを明確に区別して理解することが求められます。
これらの頻出項目を重点的に復習すれば、効率よく得点を伸ばせるはずです。
点数を伸ばすための裏ワザテクニック
都立入試の理科で点数を伸ばすには、知識の暗記だけでなく、解答を効率的に導き出すための「裏ワザテクニック」が非常に有効です。
これまで「理科は苦手だから…」と諦めかけていた方も、これから紹介するテクニックを知るだけで、得点力が大きく変わるかもしれません。
なぜなら、都立高校入試の理科には、問題の形式や出題傾向に一定のパターンが存在するからです。
一見すると複雑に見える問題でも、実は問題文の中に答えのヒントが隠されていたり、基本的な知識の組み合わせで解けたりすることが少なくありません。
この「隠れたヒント」を素早く見つけ出す力が、得点アップに直結するのです。
具体的には、実験考察問題では、結果のグラフや表の「変化が最も大きい部分」や「変化がない部分」に着目するだけで、設問の意図が見えてくることがあります。
また、4択の選択肢問題では、「すべて」「必ず」といった断定的な表現を含む選択肢は間違いである可能性が高いというセオリーも存在しました。
こうしたテクニックは、知識が少し曖昧な場合でも、消去法によって正答率を格段に引き上げてくれるでしょう。
計算問題攻略!簡単暗記法
理科の計算問題は、公式を覚えれば確実に得点源に変わる分野です。
特に物理で頻出するオームの法則は、電圧(V)・電流(I)・抵抗(R)を三角形の図に当てはめて視覚的に記憶する方法が有効でしょう。
求めたいものを指で隠せば、残りの関係性が一目でわかります。
電力(W)を求める「W = V × A」も、必ずセットで押さえておきたい公式といえます。
化学でよく出る「質量パーセント濃度」は、単に記号で覚えるのではなく、「(溶けている物質の質量 ÷ 全体の質量)× 100」と、言葉の意味と関連付けて理解するのが忘れないコツとなります。
そして何より大切な裏ワザは、問題文の「単位」に細心の注意を払うこと。
例えば、電流が「200mA(ミリアンペア)」とあれば、計算前に必ず「0.2A(アンペア)」へ変換する習慣をつけましょう。
この一手間がケアレスミスを防ぎ、ライバルとの差を生み出すのです。
作図・記述問題の解き方
都立入試の理科で差がつく作図・記述問題には、明確な攻略法が存在します。
作図問題では、フリーハンドは絶対に避け、必ず定規を使いましょう。
特に「光の屈折」や「力の分解・合成」といった頻出テーマでは、補助線や矢印を正確に描くことが得点に直結するのです。
一方、記述問題で求められるのは、単なる知識ではありません。
「なぜなら~だから。
」というように、原因と結果を論理的に結びつけて説明する力が試されます。
問題文で指定されたキーワード、例えば「飽和水蒸気量」といった語句は、必ず解答に含めるように意識してください。
完璧な解答を目指すあまり白紙で提出するのではなく、関連するキーワードを書くだけでも部分点をもらえる可能性があるため、最後まで諦めない姿勢が合格を引き寄せます。
解答欄の大きさに惑わされず、要点を簡潔にまとめる練習も非常に効果的でしょう。
実験問題の頻出パターン
都立入試の理科において、実験問題は得点源にしやすい分野です。
なぜなら、出題される実験には特定のパターンがあり、そのポイントさえ押さえれば、安定して高得点を狙えるようになるからでしょう。
例えば化学では、「炭酸水素ナトリウムの熱分解」や「うすい塩酸と石灰石の反応」が頻出テーマとして挙げられます。
これらの実験では、発生する気体の性質や、実験器具を特定の方法で設置する理由などが繰り返し問われる傾向にあります。
物理分野であれば、「電熱線の発熱量」を計算させる問題は定番中の定番といっても過言ではありません。
ここでは、電力(W)と時間(s)の関係から熱量(J)を導き出す基礎的な理解が試されるのです。
生物の実験では、光合成を証明するためにオオカナダモとBTB溶液を使った問題がよく見られます。
単に結果を暗記するだけでなく、「なぜこの結果になるのか」という背景まで理解しておくことが、応用問題に対応する鍵となります。
理科分野別の勉強法と裏ワザ
都立入試の理科で高得点を狙うには、物理・化学・生物・地学の4分野それぞれに合わせた効率的な勉強法と裏ワザを実践することが最も重要です。
すべての分野を同じ熱量で勉強するのではなく、出題傾向やあなたの得意・不得意に合わせた対策を講じることで、賢く得点を伸ばしていきましょう。
なぜなら、各分野では問われる知識の質や問題形式が大きく異なるからです。
例えば、物理では公式の理解と計算力が求められる一方、生物や地学では正確な知識の暗記が中心となる問題も少なくありません。
このように分野ごとの特性を理解し、学習の優先順位をつけることが、限られた時間で成果を出すための秘訣なのです。
具体的には、化学分野では頻出の計算問題をパターン化して覚えたり、生物分野では実験器具の正しい使い方を写真とセットで記憶したりする方法が有効でしょう。
このように、それぞれの分野には即効性の高い攻略法が存在します。
物理・化学分野と生物・地学分野に分けて、明日から実践できる勉強法と得点アップに繋がる裏ワザを以下で詳しく解説していきます。
模試や過去問で傾向を掴む
都立入試の理科で得点を伸ばす最も確実な方法は、過去問と模試の徹底的な分析にあります。
まずは最低でも過去5年分、理想を言えば10年分の過去問に挑戦してみましょう。
このとき、必ず時間を計り、本番さながらの緊張感で取り組むことが大切です。
大問1は小問集合、大問2以降は物理・化学・生物・地学の各分野から出題されるという構成は毎年ほぼ変わりません。
解き終わった後は、単に答え合わせをするだけでなく、なぜ間違えたのかを徹底的に分析してください。
知識不足なのか、計算ミスなのか、それとも問題文の読解ミスなのか原因を突き止めます。
VもぎやWもぎなどの公開模試は、自分の弱点を客観的に把握する最適なツールです。
偏差値だけでなく、分野ごとの正答率に注目し、苦手な単元を明確にして集中的に復習することで、効率よく得点力を向上させられるでしょう。
物理:公式と単位変換のコツ
都立入試の物理分野で多くの受験生が苦手とするのが、公式の暗記と単位変換ではないでしょうか。
これらの攻略には、ただ覚えるだけでなく、意味を理解する工夫が欠かせません。
例えば、「圧力 P = 力 F ÷ 面積 S」という公式は、「同じ力でも面積が小さいほど圧力は大きくなる」と画鋲の針が刺さる原理でイメージすると忘れにくくなるでしょう。
また、「み・は・じ(道のり・速さ・時間)」のような三角形の図を自分で書いて視覚的に覚えるのも有効な手段となります。
単位変換では、特に「1N/㎡ = 1Pa」や「1kg = 1000g」、「1分 = 60秒」といった基本的な関係を瞬時に思い出せるようにしておく必要があります。
問題文で与えられた単位(例:cm)と、公式で使う単位(例:m)が違うケースは頻出するため、計算を始める前に単位を揃える癖をつけましょう。
こうした地道な練習が、物理の得点を着実に伸ばす鍵なのです。
化学:化学反応式の覚え方
都立入試の化学分野で得点源となるのが、化学反応式を正確に書く力でしょう。
丸暗記に頼らず、頻出のパターンから攻略していくのが賢い方法です。
特に、水の電気分解(2H₂O → 2H₂ + O₂)や炭酸水素ナトリウムの熱分解(2NaHCO₃ → Na₂CO₃ + H₂O + CO₂)は、必ず書けるようにしておくべき重要な式となります。
もし覚えにくいと感じたら、語呂合わせを使ってみるのも一つの手。
「酸化銀さん(2Ag₂O)、しわくちゃの銀(4Ag)と酸素(O₂)にサヨナラ」のように、イメージと結びつけて記憶するのです。
また、係数を合わせる際は、最も複雑な化学式の係数を1と仮定し、そこから他の原子の数を調整していくとスムーズに進みます。
特に酸素原子(O)の数は最後に合わせると、計算が楽になるケースが多いので試してみてください。
何度も手を動かして書くことで、化学反応式は確実にあなたの武器になります。
生物:語呂合わせで重要語句暗記
都立入試の理科、特に生物分野は覚えるべき重要語句が多く、多くの受験生が苦戦します。
そんな生物の暗記には、昔ながらの「語呂合わせ」が絶大な効果を発揮するのです。
例えば、複雑な消化酵素の働きは「だいたん、いし、小鳥死亡」と覚えると忘れません。
これは「唾液はデンプン」「胃液はタンパク質」「小腸はタンパク質と脂肪」を分解するという意味になります。
脊椎動物の進化の順番も「魚両爬鳥乳(ぎょりょうはちょうにゅう)」とリズムで記憶すると簡単でしょう。
植物の分類で悩んだら、「アブラナ、タンポポ、エンドウは離弁花」のように、自分だけの面白い語呂合わせを作ってみるのも記憶に定着しやすくなる裏ワザです。
自分で作ったものは愛着が湧き、忘れにくくなる効果も期待できます。
ただし、語呂合わせだけに頼らず、その用語が持つ意味までしっかり理解しておくことが、応用問題に対応する力を養う鍵となります。
語呂合わせをうまく活用し、効率的に得点アップを目指してください。
地学:天体・地層の図解対策
地学分野の図解問題は、ポイントさえ掴めば確実に得点源に変わります。
特に頻出の天体と地層は、図を自分で描いて理解するのが一番の近道でしょう。
例えば、太陽の年周運動や金星の見え方は、北極側から見た模式図に公転の向きである「反時計回り」と書き込むだけで、位置関係が一目瞭然になります。
この「書き込み」こそが、思考を整理する最大の裏ワザなのです。
また、地層の傾きを問う柱状図問題は、まず火山灰などの「鍵層」に印をつけ、標高を基準に図を並べ替える手順を徹底してください。
この一手間で正答率が劇的に向上するはず。
さらに、「中生代ならアンモナイト」のように、示準化石と時代はセットで完璧に暗記しておきましょう。
複雑な図も、分解して考えれば必ず解けます。
試験直前に確認すべきポイント
試験直前は新しい問題に手を出すのではなく、今まで学習してきた知識の最終確認に徹することが、本番での得点力を最大化する裏ワザです。
直前期の焦りから、あれもこれもと手を広げたくなる気持ちはよく分かります。
しかし、不確かな知識を増やすよりも、確実に解ける問題を一つでも多く物にすることが合格への近道となるでしょう。
本番で「見たことはあるけど、思い出せない」という状況を避けることが重要です。
具体的には、過去問で間違えた箇所の見直しや、自分がまとめたノートの読み返しが非常に効果的でした。
特に、都立理科で頻出の実験器具の名称と使い方、重要な化学反応式、そして物理の公式は、最終チェックリストを作成して直前に見直すだけでも安心感が違います。
また、作図問題や短文記述問題の解答手順を再確認しておけば、ケアレスミスによる失点を確実に防げるでしょう。
前日・当日に確認すること
試験前日は、新たな知識を詰め込むのではなく、これまで学習した内容の最終確認に徹しましょう。
使い込んだ参考書やノートをパラパラと見返し、特に間違えやすかった問題や付箋を貼った重要項目を重点的にチェックするのが効果的です。
理科の思考問題で頭をフル回転させるため、夜更かしは絶対に避けてください。
最低でも6時間以上の睡眠を確保し、心身ともにベストな状態で当日を迎える準備が求められます。
持ち物リストも最終確認し、受験票や筆記用具、コンパス、定規などを忘れないようにしましょう。
試験当日の朝は、脳のエネルギー源となるブドウ糖を補給するため、必ず朝食を摂るようにしてください。
会場へ向かう電車の中など、少しの時間を利用して、暗記カードや自作のまとめノートに目を通すのがおすすめです。
これは新しいことを覚えるためではなく、記憶を定着させ、自信をつけるための最終儀式となります。
特に化学反応式や物理の公式、生物の重要語句など、直前の見直しで得点に繋がりやすい分野を確認すると良いでしょう。
持ち物と覚え直しリスト
試験当日の持ち物チェックは、精神的な落ち着きを保つために欠かせない準備です。
受験票やHBの鉛筆またはシャープペンシル(芯も忘れずに)、消しゴム2個、そして時計は必ずカバンに入れてください。
都立入試の理科では作図問題が出題されるため、定規とコンパスも持参が許可されています。
また、休憩時間の糖分補給にチョコレート、体を冷やさないためのカイロなども準備しておくと万全でしょう。
直前の見直し用リストとして、A4用紙1枚に要点をまとめた自作シートが効果を発揮します。
物理のオームの法則(V=IR)や電力の公式、化学の主要な化学反応式、生物の消化酵素一覧、地学の前線の記号など、忘れがちな重要項目を書き出しておくのです。
試験会場へ向かう電車の中や休み時間に最終確認することで、最後の1点を掴み取ることが可能となります。
都立入試理科のよくある質問と回答
都立入試の理科対策を進める中で、様々な疑問や不安が生まれるのはごく自然なことです。
ここでは、多くの受験生や保護者の方から寄せられる「よくある質問」とその回答を丁寧に解説しました。
あなたの悩みを解消し、スッキリした気持ちで学習に集中できるようになるでしょう。
試験が近づくにつれて、「今さらこんな基本的なことを聞いてもいいのかな?」と不安に感じてしまう方もいるかもしれません。
しかし、あなたが抱える疑問は、他の受験生も同じように感じている可能性が非常に高いのです。
小さな疑問でも決して放置せず、一つひとつ着実に解決していくことが、本番で実力を最大限に発揮するための鍵となります。
例えば、「計算問題はどのレベルまで対策すべきか」「暗記分野は直前期に詰め込んでも間に合いますか?」といった学習内容に関する質問は非常に多いです。
また、「過去問は何年分くらい解けば合格点に届きますか?」や「時間配分で気をつけるべきことは?」といった、より実践的な悩みもよく耳にします。
これらの具体的な疑問に明確に答えることで、あなたの学習計画をより確かなものにしていきましょう。
都立高校の理科の難易度について
都立高校の理科は、一部の難関校を除いて標準的な難易度の問題が中心です。
実際に、令和6年度(2024年度)入試における理科の平均点は61.7点で、これは5教科の中で国語に次いで2番目に高い数値でした。
このことからも、高得点での争いになりやすい科目といえるでしょう。
問題構成は物理・化学・生物・地学の4分野からバランス良く出題され、大半が教科書の基礎知識を問うものとなっています。
しかし近年、単なる暗記だけでは解けない実験結果の考察や作図、短文での記述を求める問題が増加する傾向にあります。
こうした「思考力・判断力・表現力」を試す問題が、ライバルと差をつけるポイントになるかもしれません。
奇問・難問は少ないですが、ケアレスミスが許されないため、基礎を固めて確実に得点することが合格の鍵を握っています。
自宅学習での進め方と注意点
自宅学習を成功させる鍵は、綿密な学習計画にあります。
まず、東京都教育委員会のウェブサイトで公開されている過去問を最低でも5年分解き、自分の実力と苦手分野を正確に把握することから始めましょう。
特に、大問1の小問集合は幅広い知識が問われるため、ここで失点しない基礎力が不可欠です。
苦手分野が判明したら、教科書や参考書に立ち返り、基礎から徹底的に復習してください。
その後、再び同じ過去問に挑戦し、どれだけ理解が深まったかを確認するサイクルが実力アップにつながります。
注意したいのは、一人だとどうしても得意分野ばかりに時間を割いてしまう点でしょう。
物理の計算や化学反応式といった、時間のかかる問題から逃げずに取り組む勇気が求められます。
週単位で計画を見直し、着実に弱点を克服していくことが合格への近道となるのです。
塾に通わずに合格する方法
塾に通わなくても都立入試の理科で合格点を獲得することは十分に可能です。
そのための鍵は、「良質な教材選び」と「徹底した過去問分析」の2点にあります。
まずは東京都教育委員会のウェブサイトから最低でも過去5年分の問題を手に入れ、出題傾向や時間配分を身体で覚えましょう。
教材は、教科書準拠のワークで基礎を固め、『全国高校入試問題正解』のような実践的な問題集を1冊完璧に仕上げるのが効果的となります。
独学でつまずきやすい不明点は、決して放置してはいけません。
学校の先生に積極的に質問したり、オンラインの映像授業を苦手分野の克服に活用したりと、使えるものは全て利用する姿勢が重要です。
物理・化学・生物・地学の4分野をバランス良く学習する計画を立て、着実に実行することが合格への最短ルートになるでしょう。
まとめ:都立入試の理科は裏ワザで得点アップを狙おう
今回は、都立入試の理科で点数を伸ばしたいと考えている方に向け、- 時間を有効に使うための解答順序- 大問ごとの具体的な攻略テクニック- 知識を定着させる効率的な暗記法上記について、解説してきました。
都立入試の理科で高得点を取るためには、単に知識を詰め込むだけでは不十分な場合があります。
実は、出題傾向に基づいた得点に直結しやすい解き方の「コツ」が存在するのです。
これまで勉強してもなかなか成果が出ず、焦りを感じていた方もいるかもしれません。
しかし、心配する必要はありませんでした。
この記事で紹介した「裏ワザ」とも言えるテクニックを、ぜひ一つでも実践してみてください。
きっと、これまでとは違う手応えを感じられるでしょう。
あなたが今まで積み重ねてきた学習は、確かな土台となっています。
その努力に、少しの工夫と戦略を加えるだけで、結果は大きく変わってくるもの。
正しい方法で対策すれば、理科は心強い得点源に変わる可能性を秘めています。
合格への道筋が、より明確に見えてくることでしょう。
さっそく、次の学習から今日お伝えした方法を試してみましょう。
万全の準備で本番に臨み、志望校合格を勝ち取ることを筆者は心から応援しています。