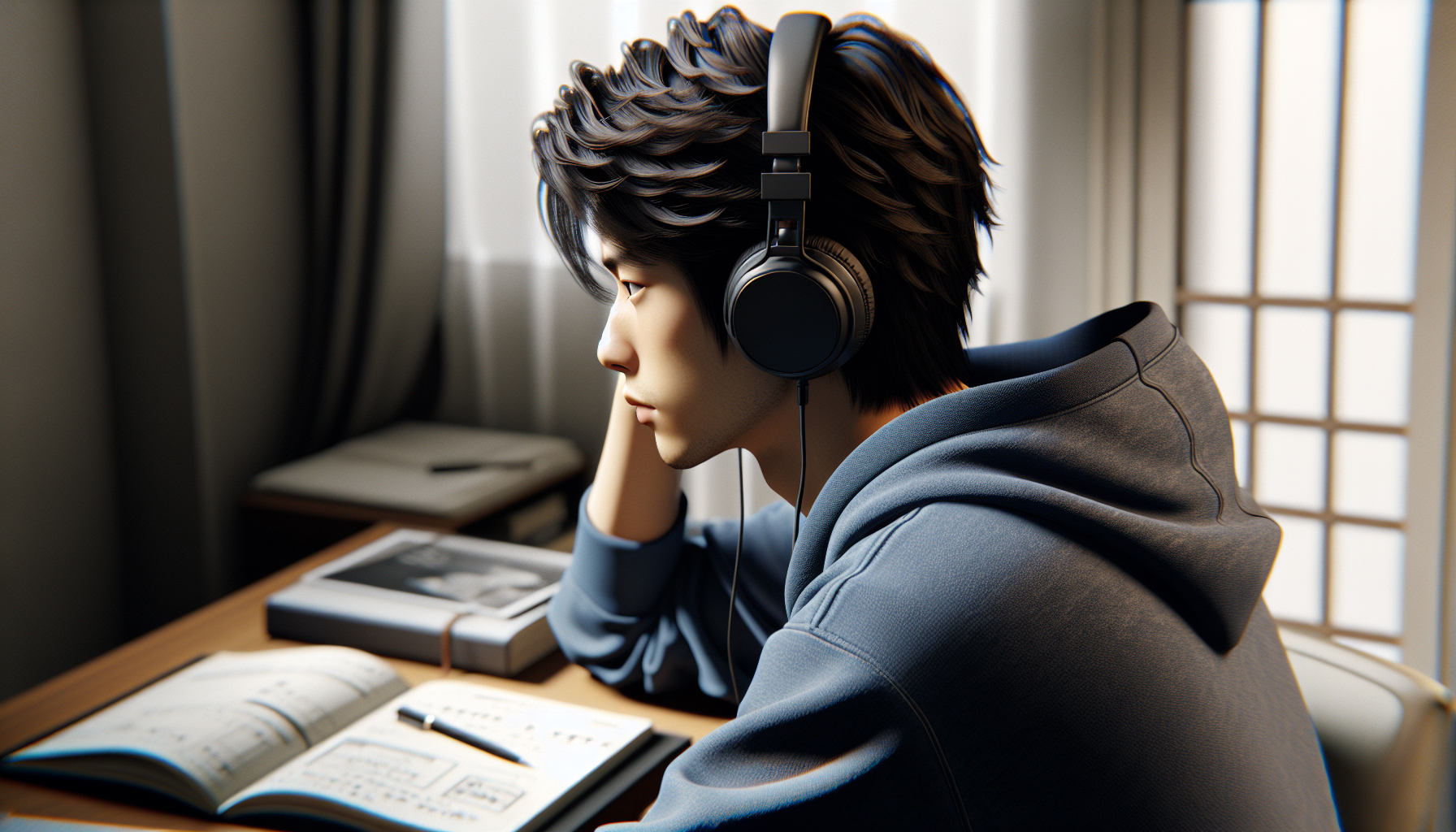共通テストのリスニングが近づくにつれ、「本番でちゃんと聞き取れるか心配…」あるいは「少しでも点数を稼げる裏技があれば知りたい」と感じている方もいるでしょう。
配点が高いリスニングは、合否を分ける重要な科目の一つです。
しかし、いくつかのコツを知っているだけで、本番の得点力は大きく変わる可能性があります。
今からでも決して遅くはありません。
この記事では、共通テストのリスニングで高得点を狙いたいと考えている方に向けて、
– 問題文と選択肢を先読みするテクニック
– 音声が流れる前に準備しておくべきこと
– 解答に迷ったときの思考法
上記について、解説しています。
今回ご紹介する内容は、誰でもすぐに実践できる簡単なものばかりです。
本番で焦らず、落ち着いて実力を発揮できるようになるためのヒントが詰まっていますので、ぜひ参考にしてください。
共通テストリスニングの基本情報を理解しよう
共通テストのリスニングで高得点を狙うには、まず試験の基本的なルールや特徴を正確に把握することが不可欠です。
焦ってテクニックだけを追い求める前に、まずは敵を知ることから始めましょう。
どのような試験なのかを知ることで、自分に合った効果的な対策が立てやすくなります。
その理由は、問題構成や配点、音声が読まれる回数といったルールを知らないままでは、本番で実力を十分に発揮できない可能性があるからです。
「なんとなく聞いて解いている」という状態では、時間配分を間違えたり、どの問題に集中すべきか判断できなかったりするかもしれません。
具体的には、試験時間は30分、配点はリーディングと同じ100点という大きなウェイトを占めます。
そして、第1問と第2問は音声が2回放送されるのに対し、グラフの読み取りなど思考力が問われる後半の第3問から第6問は1回しか放送されないという大きな違いがあるのです。
この基本情報を知っているかどうかが、高得点を取るための最初の分かれ道と言えるでしょう。
リスニング問題の概要と特徴
共通テストのリスニングは、リーディングと同じく100点の配点が割り振られている重要な科目です。
試験時間は解答に使える30分間で、問題は全6問から成り立っています。
最大の特徴として挙げられるのが、音声の読み上げ回数でしょう。
第1問と第2問は音声が2回流れるのに対し、第3問から第6問までは1回しか読み上げられません。
そのため、後半に進むにつれて高い集中力が求められるようになります。
また、アメリカ英語だけでなく、イギリス英語や非ネイティブ話者による多様な発音が出題される点も、旧センター試験とは大きく異なるポイントだといえるでしょう。
単純な会話の聞き取りにとどまらず、講義内容の要約やグラフの読み取りといった、思考力を試す問題が出題される傾向にあります。
時間配分の重要性
共通テストのリスニング試験は、解答時間30分で全6問を解ききるスピード勝負です。
この短い時間で高得点を獲得するには、1秒たりとも無駄にできない時間配分が鍵を握ります。
特に重要なのが、問題の音声が流れる前に設問と選択肢に目を通す「先読み」の時間でしょう。
問題と問題の間のわずかな時間で、次に何が問われるのか、どのような情報を聞き取るべきかを把握しておくのです。
この準備があるかないかで、正答率は大きく変わってきます。
例えば、第1問や第2問は比較的易しいため、ここでリズムを作り、情報量が多くなる第3問以降に備える意識が求められます。
特に1回しか放送されない問題では、迷っている時間はありません。
30分という時間を最大限に活かす戦略を立て、本番さながらの練習を繰り返すことが、高得点への道を切り拓くのです。
リスニング高得点を狙うための3つの裏技
共通テストのリスニングで高得点を獲得するために、ネイティブ並みのヒアリング能力は必ずしも必要ありません。
実は、試験の特性を理解した上で、少しの工夫とテクニック、つまり「裏技」を知っているかどうかが点数を大きく左右するのです。
「英語の音声が速くて聞き取れない」と悩んでいる方も、今回ご紹介する3つのコツを実践すれば、驚くほど楽に正解を選べるようになるでしょう。
その理由は、共通テストのリスニング問題には毎年繰り返される出題傾向や、受験生を惑わせるための巧妙な仕掛けが存在するからです。
多くの受験生は流れてくる音声を懸命に聞き取ろうとすることに集中しすぎてしまい、設問の意図や選択肢の微妙な違いを見落としてしまいがちでした。
しかし、事前に問題の構造を把握し、どこに注意して聞けばよいかを理解しておくだけで、焦らずに解答の根拠を見つけられるようになります。
具体的には、問題音声が始まる前のわずかな時間に、設問と選択肢から会話の内容を予測するテクニックが挙げられます。
例えば、選択肢に「at the library」や「in the classroom」のような場所を表す語句が並んでいれば、場面を特定する問題だと瞬時に判断できるでしょう。
また、読み上げられる英文の数字や固有名詞だけに集中するのではなく、話者の感情や意見を表す表現に注目することも、正解率を上げるための重要な裏技の一つです。
事前準備で差をつける方法
共通テストのリスニングで高得点を狙うには、音声が流れる前の準備時間が勝負の分かれ目となります。
問題冊子が配られてから試験が開始されるまでの約10分間を最大限に活用しましょう。
この時間で、まず全ての設問と選択肢に目を通すことが極めて重要です。
特に、第3問以降の図や表が含まれる問題は、先に情報を整理しておくと、音声の内容を格段に理解しやすくなります。
具体的には、設問文中の疑問詞(Who, What, Whyなど)や数字、固有名詞といったキーワードに丸をつけ、何を聞き取ればよいのかを明確にしておきましょう。
選択肢を比較し、相違点に下線を引いておくのも効果的な方法です。
例えば、「go to the museum」と「go to the library」のように動詞や場所が異なる選択肢があれば、そこが聞き取りの焦点になります。
この「先読み」という一手間を加えるだけで、音声を聞きながら焦って問題文を読む必要がなくなり、解答の精度が飛躍的に向上するでしょう。
音声を効率的に聞き取るテクニック
リスニング音声が流れた際、ただ漠然と全体を聞き取ろうとするのは非効率的です。
解答に必要な情報をピンポイントで聞き出す意識を持つことが重要になります。
そのために最も効果的なテクニックが、音声が流れる前の「先読み」でしょう。
問題冊子の設問や選択肢に素早く目を通し、「何が問われているのか」を事前に把握しておくだけで、聞くべきポイントが明確になるのです。
例えば、時刻を問う問題なら数字に、場所を問う問題なら地名に意識を集中させられます。
また、音声を聞きながら明らかに違う選択肢を消していく「消去法」も有効なテクニックです。
さらに、会話の中で逆接を示す「but」や「however」といった単語の直後には、話者の本音や重要な情報が現れるケースが非常に多いという特徴があります。
このような話の流れを変える言葉に注意を払う訓練も効果的です。
日頃の学習から、キーワードを意識して聞き取る練習を繰り返すことで、本番でも自然と実践できる力が身につくでしょう。
ワークシートを活用した解答法
共通テストのリスニングで高得点を狙う鍵は、問題用紙にあるワークシートの効果的な活用にあります。
音声が流れる前の貴重な時間で、ワークシート全体を素早く確認してください。
特に第5問の講義形式では、ワークシートの構成が講義の流れそのものを表している場合が多く、空欄の前後にある単語から聞き取るべき内容を予測できるでしょう。
音声を聞きながら、完璧な文章でメモを取る必要は全くありません。
聞き取れたキーワードや数字、記号などを使い、自分だけが分かる形で素早く書き留めることが重要です。
複数の意見が出てくる場面では、「A:賛成」「B:反対」のように話者の頭文字と記号で記録すれば、後から状況を瞬時に把握できます。
このようにワークシートを「音声の地図」として先読みし、情報を整理するツールとして使いこなすことこそ、正答率を飛躍的に高める裏技となるのです。
リスニング第5問を攻略するコツ
共通テストリスニングの第5問は、講義形式の長い音声を聞いてワークシートを完成させる問題で、苦手意識を持つ受験生も少なくありません。
しかし、高得点を狙うための最も重要なコツは、音声が流れる前にワークシートを完璧に読み込み、聞くべきポイントを予測しておくことです。
この事前の準備が、正答率を大きく左右するカギとなります。
その理由は、第5問で流れる音声は情報量が非常に多く、ただ漫然と聞いているだけでは重要な情報を聞き逃してしまう可能性が高いからです。
「何について話しているのか」「どの情報を聞き取るべきか」という目的意識を明確に持つことで、一度しか流れない音声の中から必要な情報だけを効率的に拾い上げることができるようになるでしょう。
具体的には、ワークシートの空欄部分だけでなく、その前後の文章や図表のタイトル、選択肢にまでしっかりと目を通しておくことが大切です。
例えば、空欄(34)の前に「原因」という単語があれば、音声中の “because” や “the reason is…” といった表現に集中すれば良いのです。
このように、聞くべきポイントに狙いを定めることで、解答の根拠を的確に見つけ出すことが可能になります。
講義の聞き取りポイント
共通テストリスニングの第5問は、まとまった内容の講義を聞き取り、設問に答える形式です。
音声は1回しか放送されないため、聞き取るべきポイントを事前に押さえておくことが高得点のカギとなります。
まず最も重要なのは、講義の冒頭部分でしょう。
最初の30秒ほどでテーマや全体の流れが説明されるので、ここで話の全体像を掴むことが求められます。
次に、話の展開を示す接続詞に注目してください。
“First” “Second” “However” “In conclusion” といった言葉は、話の構造を理解する上で強力な道しるべになるのです。
これらの言葉が聞こえたら、ワークシートに印をつけるなど工夫すると良いでしょう。
また、講義を通して話者が何を最も伝えたいのか、その結論を常に意識しながら聞く姿勢も欠かせません。
この3点を実践するだけで、複雑な講義内容でも格段に理解しやすくなるはずです。
空欄を埋めるテクニック
第5問の空欄補充では、音声の内容を正確に聞き取る力に加えて、文脈から答えを推測する能力が試されます。
音声が流れる前に、必ずワークシートの空欄の前後を確認し、どのような品詞(名詞、動詞など)や内容(数字、人名など)が入るか予測しておくことが重要でしょう。
この一手間が、聞くべきポイントを絞る大きな助けとなります。
講義が始まったら、特に「First」や「The main cause is」といった話の展開を示す言葉や、具体的な数字、固有名詞は聞き逃さないようにメモを取ることをおすすめします。
全ての単語を書き取る必要はなく、キーワードを拾う意識が大切です。
また、共通テストでは、音声で使われた単語がワークシートでは同じ意味の別の単語(パラフレーズ)に置き換えられているケースが頻出します。
例えば、音声で「increase」と流れても、選択肢では「rise」と表現されるかもしれません。
この言い換えに気づけるかが、正解への大きな鍵を握っているのです。
共通テストの裏技に関するQ&A
共通テストのリスニングで使える「裏技」について、本当に効果があるのか、使っても問題ないのかといった疑問や不安を感じていませんか。
このセクションでは、そんなあなたの悩みを解決するため、よくある質問にQ&A形式でわかりやすくお答えします。
安心して本番に臨むために、ここで疑問点をすべて解消していきましょう。
なぜなら、裏技やテクニックは正しく理解して使ってこそ、初めてその効果を発揮するからです。
ただ闇雲に聞きかじった方法を試すだけでは、かえって混乱を招き、点数を落としてしまう危険性も否定できません。
本番で自信を持って実力を出し切るためには、テクニックの根拠や注意点をしっかりと把握しておくことが何よりも大切なのです。
具体的には、「問題冊子の余白への書き込みはどこまで許されるのか」といったルールに関する質問や、「紹介されたテクニックが自分のレベルに合っているかどうかの判断基準」といった実践的な悩みを取り上げます。
また、「裏技を使っても時間が足りない場合はどうすればいい?」など、多くの受験生が直面するであろう課題についても回答を用意しました。
リスニングの勉強法は?
リスニング力を飛躍的に向上させるには、日々のトレーニングが欠かせません。
まず試してほしいのが、英語音声のすぐ後を追って発音する「シャドーイング」です。
これにより、英語特有のリズムやイントネーションが自然と身につくでしょう。
さらに、聞き取った音声を書き起こす「ディクテーション」を組み合わせると、冠詞の聞き逃しや音声変化など、自分の弱点が明確になります。
共通テスト独特の形式に慣れることも極めて重要です。
過去問やZ会、河合塾が出版する予想問題集を使い、必ず時間を計って解く練習を重ねてください。
1回しか読み上げられない第3問以降で、いかに情報を正確に聞き取るかという実践的な訓練になります。
学習を続けるには、楽しみながら英語に触れるのが効果的です。
通学中にNHK WORLD-JAPANのニュースを聞いたり、興味のある分野のTED Talksを視聴したりする習慣を取り入れ、英語耳を育てていきましょう。
裏技を使う際の注意点は?
共通テストのリスニングで裏技を使う際は、それが万能ではないと理解しておく必要があります。
テクニックに過度に依存してしまうと、かえって音声の重要な部分を聞き逃す危険性も出てくるでしょう。
例えば、選択肢の先読みに集中しすぎるあまり、肝心なキーワードを聞き取れないといった失敗は避けたいところです。
2021年度以降の共通テストでは、単なる情報聴解だけでなく、思考力や判断力を試す問題も増えているため、小手先の技だけでは対応しきれない場面が想定されます。
紹介した裏技は、大学入学共通テストの過去問や最低3回分の予想問題集などで必ず事前に練習し、自分に合うかどうかを確かめてください。
あくまで盤石なリスニング力の土台があってこそ活きる補助的な手段だと考え、日々の学習と並行して活用することが高得点への近道です。
まとめ:共通テストリスニングの裏技で、本番に自信を
今回は、共通テストのリスニングで思うように点数が取れず悩んでいる方に向け、- 問題文の先読みで解答を予測するコツ- 聞き取りに集中し、重要な情報を逃さないテクニック- 消去法を駆使して正答率を上げる裏技上記について、解説してきました。
この記事で紹介したコツは、少し意識するだけで誰でも簡単に実践できるものです。
特別な能力は必要なく、事前の準備や解答の進め方を工夫するだけで、聞き取る力は大きく変わるからでした。
本番が近づくにつれて、不安や焦りを感じている方もいるかもしれません。
しかし、この記事で学んだ方法を試せば、その心配も軽くなるでしょう。
まずは普段の学習から、一つでも実践してみることをおすすめします。
あなたがこれまで積み重ねてきた英語学習は、確かな土台となっています。
その努力に、今回紹介したちょっとしたコツが加わることで、実力はさらに伸びていくはずです。
本番では、きっと落ち着いて音声に集中できるようになるでしょう。
「聞き取れた」という手応えが自信につながり、結果として高得点を引き寄せてくれます。
さあ、今日から早速これらの裏技を試して、リスニングを得点源に変えていきましょう。
あなたの挑戦が成功することを、筆者は心から応援しています。