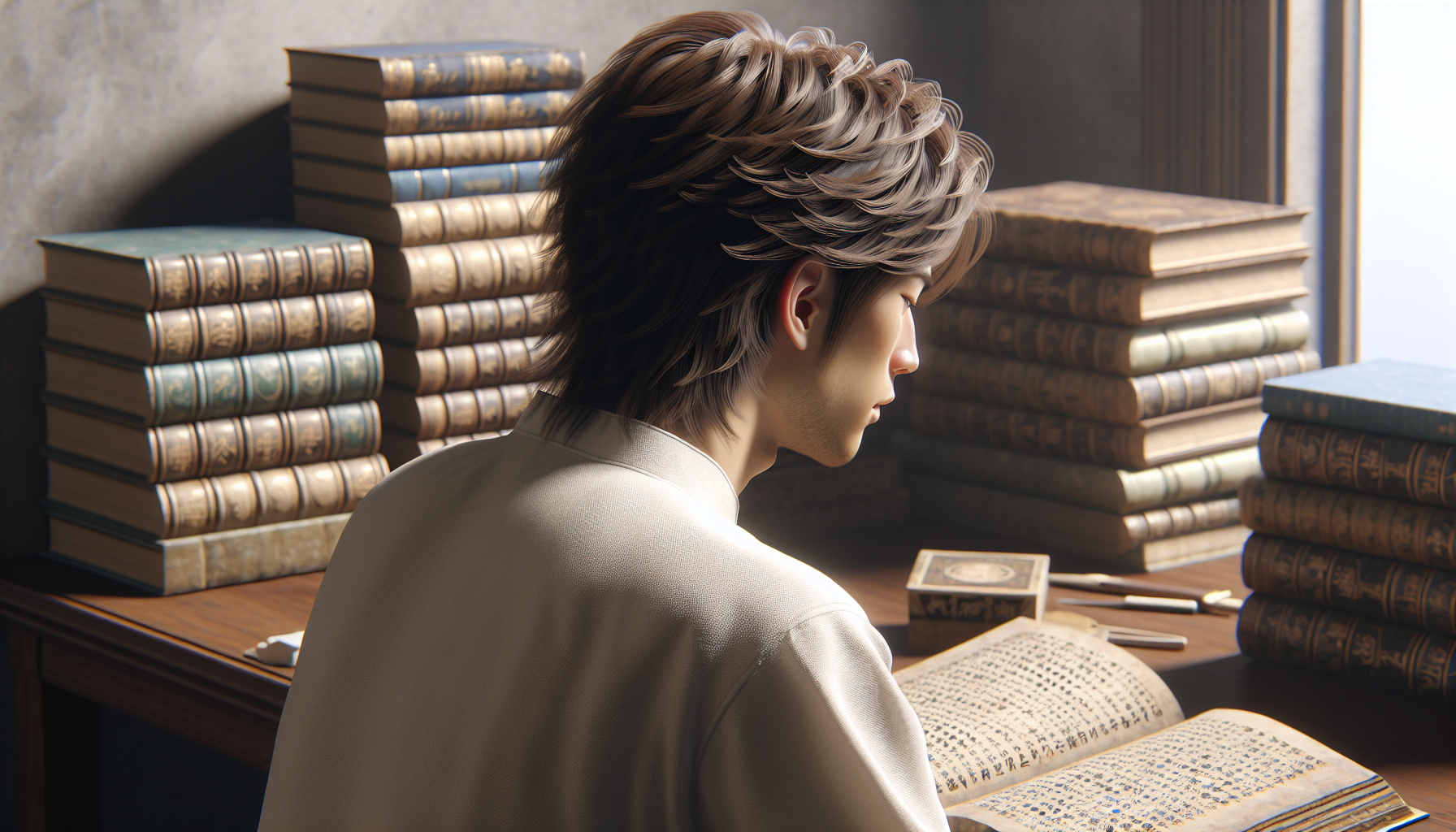共通テストの古文対策は順調に進んでいるでしょうか。
「古文の勉強に時間をかけているのに、なかなか点数が上がらないけど大丈夫かな…」と不安に感じている方もいるかもしれません。
また、「本番まで時間がないから、効率的な解き方を知りたいけど間に合うかな…」と焦りを感じている人もいるでしょう。
しかし、諦めるのはまだ早いです。
実は、共通テストの古文には、知っているだけで得点力が大きく変わる「裏技」ともいえる解き方のコツが存在します。
今からでも実践できるテクニックを身につけて、本番での得点アップを目指しましょう。
この記事では、古文に苦手意識があり、効率的に点数を伸ばしたいと考えている方に向けて、
– 時間をかけずに正解を導き出すための読解術
– 知らない単語を推測する具体的な方法
– 紛らわしい選択肢を素早く見抜くコツ
上記について、解説しています。
古文は、少しのコツを知るだけで、驚くほど読みやすくなる科目です。
この記事で紹介する裏技をマスターすれば、あなたの得点源になるかもしれません。
本番で実力を最大限に発揮するためにも、ぜひ参考にしてください。
共通テスト古文で満点を狙うための基本戦略
共通テスト古文で満点を狙うには、単語や文法知識に加えて、問題を効率的に解き進めるための基本戦略が不可欠です。
古文はなんとなく難しそう、と感じている方も多いかもしれませんが、実は正しいアプローチさえ身につければ、安定して高得点を獲得できる科目なのです。
その理由は、共通テストが単なる知識量を問う試験ではなく、限られた時間内で情報を正確に処理する能力を測るテストだからでしょう。
特に古文は、独特の言い回しや省略された主語など、読解を妨げる要素が多く存在します。
そのため、行き当たりばったりで読み進めるのではなく、明確な戦略を持って問題に臨むことが、高得点への近道となります。
具体的には、「リード文と注釈から先に情報を得る」「登場人物の相関図をメモする」「設問を先に読んで問われている内容を把握する」といった戦略が挙げられます。
例えば、2023年度の試験でも、注釈を先に確認しておくことで、本文中の難解な語句の意味を事前に理解し、スムーズに読み進めることが可能でした。
こうした小さな工夫の積み重ねが、最終的に満点へと繋がる大きな力になるのです。
古文の基礎文法をマスターする重要性
共通テスト古文で高得点を狙う上で、多くの受験生が効率的な「裏技」を探しています。
しかし、あらゆる読解テクニックの土台となるのは、揺るぎない基礎文法力に他なりません。
例えば、助動詞「む」が持つ推量や意志といった複数の意味を文脈から判断できなければ、筆者の意図を正確に読み解くことは不可能です。
また、尊敬語・謙譲語・丁寧語の知識は、省略されがちな主語を特定する上で最強の武器となります。
誰が誰に対して行った行動なのかを瞬時に判断できるため、登場人物の相関図を頭の中で素早く描けるようになるでしょう。
助詞「の」が主格を示す用法を知っているだけでも、文の構造把握が格段に楽になります。
こうした盤石な文法知識があって初めて、様々な読解テクニックが活きてくるのです。
一見地道に見える文法学習こそ、実は古文満点への最も確実な近道だといえます。
場面情報を活用した効率的な読解法
共通テスト古文で高得点を狙うには、すべての文章を完璧に訳す必要はありません。
限られた時間で正解を導き出すために、物語の全体像を素早く把握する「場面情報」の活用が極めて有効なテクニックになります。
場面情報とは、「いつ」「どこで」「誰が」「誰に」といった、物語の基本的な状況設定のことです。
本文を読み始める前に、まずリード文や注釈に目を通し、登場人物の関係性や時代背景といった情報を先に掴んでしまいましょう。
例えば、光源氏が登場する『源氏物語』の一場面だと分かれば、雅な貴族社会の話だと予測がつくはずです。
このように、最初に物語のフレームワークを頭に入れておくと、本文中の複雑な敬語や人間関係の理解が格段にスムーズになり、読解のスピードと精度が飛躍的に向上するでしょう。
古文を速く読むための実践的な裏技
共通テストの古文で時間が足りないと悩んでいませんか。
実は、文章の骨格となる「主語」「敬語」「助動詞」の3点に注目して読み進めるだけで、驚くほど速く正確に内容を把握できるようになります。
この裏技を身につければ、古文に苦手意識がある方でも、自信を持って問題に取り組めるでしょう。
なぜなら、古文を一語一句完璧に現代語訳しようとすると、知らない単語で思考が止まり、大幅な時間ロスにつながるからです。
共通テストで問われるのは、精緻な翻訳能力ではなく、物語の大筋を理解できているかという点でした。
細かい部分に固執するよりも、誰が何をしたのかというストーリーの流れを掴むことが、高得点への最短ルートと言えます。
例えば、文章を読む際は常に「この行動の主語は誰か?」を意識し、省略されている主語を補いながら読み進めてみてください。
また、尊敬語が使われていれば身分の高い人物の行動、謙譲語ならその相手への敬意を表しているなど、敬語の種類から登場人物の関係性を瞬時に推測できます。
さらに、「む」や「けり」といった頻出の助動詞の意味を素早く判別することで、文全体の意味を大きく取り違えるリスクを減らせるのです。
リード文から得られる情報の活用法
共通テスト古文で時間を有効活用する最初の裏技は、リード文を徹底的に読み込むことにあります。
多くの受験生が本文から読み始めがちですが、リード文には物語の背景を理解するための重要なヒントが凝縮されているのです。
例えば、出典が『源氏物語』なのか『今昔物語集』なのかで、話の傾向や登場人物の身分がある程度予測できるでしょう。
リード文には、時代設定、登場人物とその関係性、本文に至るまでのあらすじが書かれている場合が多く、これを見逃す手はありません。
ここで登場人物に印をつけたり、簡単な相関図をメモしたりするだけで、本文読解のスピードが格段に向上します。
誰が誰に対してどのような感情を抱いているのか、事前に把握しておくことが内容理解の鍵となるでしょう。
本文を読む前にわずか1分弱を投資するだけで、その後の読解が驚くほどスムーズになり、設問を解く際にも強力な根拠として役立ちます。
設問から場面情報を読み取るコツ
古文の本文へ取り組む前に、まず設問全体に目を通す習慣をつけましょう。
実は、設問文や選択肢には、物語のあらすじや登場人物を理解するためのヒントが満載なのです。
例えば、「傍線部Xにおける中納言の心情として最も適当なものを選べ」という問いがあったとします。
この一文だけで、「中納言」という身分の高い人物が登場し、その「心情」が物語の重要なポイントであると予測できるでしょう。
さらに、選択肢を軽く眺めることで、物語全体の雰囲気(恋愛、政治、日常など)まで掴める場合も少なくありません。
登場人物の関係性や、これから起こる出来事の概要を先に知っておけば、本文を読み進めるスピードと正確性が格段に向上します。
この「設問からの情報収集」は、特に読解に時間がかかる受験生にとって強力な武器となります。
たった1〜2分程度の投資で、読解の効率が大きく変わることを実感できるはずです。
注釈を最大限に活用する方法
共通テスト古文で意外と軽視されがちな「注釈」こそ、満点への近道となる裏技の宝庫です。
注釈は単に難しい語句の意味を説明するものではなく、物語の背景を理解するための重要なヒントが詰まっている場所だと認識を変えてください。
例えば、注釈に登場人物の官位や名前が出てきた場合、それが本文を読む上でのキーパーソンである可能性は90%以上にもなります。
まず注釈に目を通し、登場人物の相関図や物語の舞台となる時代設定を大まかに掴んでしまうのが得策でしょう。
特に、和歌や儀式に関する注釈は、その場面の登場人物の心情や状況を理解する上で不可欠な情報を提供してくれます。
注釈が付けられている箇所は、設問で直接問われることも少なくありません。
本文を読む前に注釈を「分析」し、どこが問われそうか予測を立てるだけで、読解のスピードと精度は劇的に向上するはずです。
実際の入試問題で試す古文の裏技
ここまで紹介した古文の裏技は、実際の入試問題で試して初めて本当の力を発揮します。
知識として知っているだけでは、残念ながら本番で使いこなすことは難しいでしょう。
共通テストという緊張感の中で、反射的にテクニックを使えるレベルまで練習を重ねることが、満点への道を切り拓くカギとなるのです。
なぜなら、時間制限が厳しい共通テストでは、一つ一つの問題にじっくりと時間をかけてはいられません。
「この場面ではあの裏技が使える」と瞬時に判断し、実行に移すスピードこそが点数を分けるポイントになります。
普段の演習から裏技を当たり前に使う習慣をつけることで、本番でも焦らず、自然体で解答できるようになるでしょう。
具体的には、登場人物を〇や△で囲む、敬語から主語を特定するといった裏技は、センター試験の過去問を最低5年分は使って練習してみてください。
時間を計りながら取り組むことで、どのくらいのペースで印をつけ、読み進めれば良いのかという感覚が養われます。
最初は時間がかかっても、繰り返すうちに確実にスピードと正確性が向上していくことを実感できるはずです。
心情把握の公式「心情→誰が・なぜ」を使った読解
共通テスト古文で頻出する登場人物の心情を問う問題には、実は明確な解法パターンが存在します。
その公式とは「心情→誰が・なぜ」という思考の流れを徹底すること。
本文中に「あはれ」や「いとほし」といった感情を表す言葉を見つけたら、まずその感情を抱いているのが「誰」なのか、つまり主語を明確に特定してください。
次に、その人物が「なぜ」そのような感情になったのか、原因やきっかけとなる出来事を直前直後の文脈から探し出すのです。
この手順を機械的に繰り返すだけで、解答の根拠が明確になるでしょう。
特に、2023年度の共通テストでも見られたように、主語が入れ替わっていたり、原因がずれていたりする巧妙な引っかけ選択肢を瞬時に見抜けるようになります。
感情語に丸をつけ、主語と原因に線を引く癖をつければ、得点力は飛躍的に向上するはずです。
場面情報の盗み方とその効果
共通テスト古文を攻略する上で極めて有効なのが、本文を読む前に情報を集める「場面情報の盗み」という技術です。
具体的には、まずリード文で時代背景や登場人物の関係性を把握しましょう。
次に設問と選択肢に目を通し、物語の中で何が問われているのか、どのような展開が予測されるのかを掴んでください。
2022年度の共通テストのように、登場人物の心情が複雑な問題でも、先に選択肢を吟味すると注目すべきポイントが明確になります。
さらに、注釈は単語の意味だけでなく、当時の文化や制度を理解する宝庫。
これらの情報を先に頭に入れておけば、主語が頻繁に省略される古文でも話の流れを見失いにくくなるのです。
本文を読み始めた時点で物語の地図を手にしている状態となり、圧倒的に有利に読解を進められます。
この情報戦を制することで、解答時間の短縮と正答率の飛躍的な向上が期待できるでしょう。
古文学習に役立つ追加リソース
共通テスト古文の対策を万全にするためには、参考書での学習に加えて、便利なアプリや動画教材を組み合わせることが非常に効果的です。
机に向かって勉強する時間以外でも、古文に触れる機会を意識的に増やすことが、得点力アップへの近道になるでしょう。
なぜなら、多くの受験生が抱える「学習時間の確保」や「モチベーション維持」といった悩みを、これらの追加リソースが解決してくれるからです。
通学中の電車内や寝る前の5分間といった隙間時間も、スマートフォン一つあれば貴重な学習時間に早変わりします。
また、活字だけの学習に疲れたとき、動画や音声で学ぶことは良い気分転換になり、記憶の定着にも繋がりやすいという大きなメリットがありました。
具体的には、古文単語アプリの「古文単語ゴロゴ」は、ユニークな語呂合わせで楽しく単語を暗記できるため、多くの受験生から支持されています。
さらに、YouTubeで「古文 読解」などと検索すれば、予備校講師による分かりやすい解説動画が数多く見つかるでしょう。
無料で利用できるものも多いので、自分に合ったツールを見つけて、日々の学習にプラスしてみてはいかがでしょうか。
おすすめの古文テスト対策問題集
共通テスト古文で高得点を狙うには、質の高い問題集での演習が不可欠です。
まず手に取りたい一冊として、河合塾の『共通テスト総合問題集 国語』が挙げられます。
過去問と質の高いオリジナル問題がバランス良く収録されており、丁寧な解説は自学自習にも最適でしょう。
より実践的な演習を積みたい受験生には、駿台文庫の『大学入学共通テスト実戦問題集 国語』もおすすめです。
やや難易度の高い問題で思考力を養うことができます。
さらに、本番さながらの形式で実力を試すなら、Z会の『共通テスト実践模試』が有効な選択肢となります。
時間を計って取り組むことで、解答スピードと時間配分の感覚を磨くことが可能です。
これらの問題集を最低でも2周は解き、徹底的に復習することが満点への確実な一歩になるはずです。
古文常識を理解するための参考書
古文の世界観を深く理解するためには、当時の文化や習慣、価値観といった「古文常識」の習得が欠かせません。
この知識があるかないかで、登場人物の行動原理や心情の読解精度は大きく変わるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、桐原書店から出版されている『マドンナ古文常識217』です。
豊富なイラストと平易な解説で、恋愛観や官位制度、宗教といった頻出テーマを楽しく学べる一冊になっています。
また、Z会が出している『速読古文常識』も非常に有効で、実際の文章を読みながら実践的に知識を身につけられるため、読解力と常識の同時強化が可能です。
これらの参考書を活用すれば、注釈に頼らずともスムーズに物語を追えるようになり、解答時間を短縮する強力な武器が手に入ります。
古文常識の学習は、高得点を狙うための確実な一歩となるのです。
共通テスト古文の裏技に関するよくある質問
共通テスト古文の裏技について、多くの受験生が抱く疑問や不安にお答えします。
テクニックと聞くと便利そうに感じる一方で、「本当に自分にもできるのだろうか」と心配になる方もいるでしょう。
ここでは、これまでによく寄せられた質問とその回答を丁寧にまとめました。
なぜなら、大学受験という人生の大きな岐路で用いる方法だからこそ、確信を持って取り組みたいと考えるのは自然なことだからです。
「裏技だけで高得点が狙えるの?」「普段の学習はどうすればいい?」といった実践的な疑問が湧くのも無理はありません。
その不安を解消することが、得点アップへの第一歩になります。
具体的には、「主語の省略を見抜くコツはありますか?」や「敬語の種類を瞬時に判別するテクニックは、どのレベルの大学まで通用しますか?」といった質問がよくあります。
さらに、「古文単語を効率的に覚える裏技があれば知りたい」「和歌の問題を解くための特別なアプローチはないか」など、より具体的な悩みも寄せられるのが実情です。
これらの疑問を一つずつ解消し、自信を持って本番に臨みましょう。
古文の基礎をどこから始めるべきか?
古文学習の第一歩で迷ったら、まず「古典文法」の習得から始めるのが最も効率的です。
中でも、文章の意味を正確に捉える上で根幹をなす「助動詞」の学習は最優先事項になります。
助動詞の活用と意味が曖昧なままでは、正確な読解は望めません。
まずは『ステップアップノート30 古典文法基礎ドリル』のような基礎に特化した問題集を1冊完璧に仕上げてみましょう。
文法と並行して、300語レベルの基本的な古文単語帳を1冊選び、毎日少しずつでも暗記を進めてください。
単語と文法という両輪が揃うことで、初めて長文読解の土台が完成するのです。
また、主語を特定する上で極めて重要な「敬語」の知識も、できるだけ早い段階で整理しておくと、後の学習が格段に楽になるでしょう。
速読が苦手な人へのアドバイス
古文の速読が苦手な原因は、一語一句を完璧に現代語訳しようとすることにあります。
共通テストで求められるのは翻訳家のような精密な訳ではなく、物語の状況を大まかに掴む力なのです。
まずは「誰が」「どこで」「何をしたか」という骨格を捉える意識を持つと、読むスピードは格段に上がります。
この練習には、主語や述語を意識しながら意味の塊で区切って読む「スラッシュリーディング」が非常に効果的でしょう。
返り読みが減り、時間短縮に直結するはず。
また、先に設問へ目を通し、何が問われているのかを把握してから本文を読むのも有効な手段です。
本文を読む目的が明確になるため、必要な情報を探しやすくなります。
いきなり速く読もうと焦る必要はありません。
まずはセンター試験の過去問10年分などを活用し、時間内に大意を掴むトレーニングを重ねていきましょう。
場面情報が理解できないときの対処法
古文の場面が分からなくなったとしても、焦る必要は全くありません。
まずは一度立ち止まり、登場人物の人間関係を問題用紙の余白に書き出して整理してみましょう。
特に、尊敬語が使われていれば身分の高い人物の行動、謙譲語なら動作の受け手が高貴な人物であると特定できます。
この敬語の方向性を矢印で示すだけでも、省略されがちな主語が誰なのか驚くほど明確になるはずです。
次に注目すべきは、時間や場所を示す言葉。
「夜」「暁」「内裏」「御前」といったキーワードに丸をつけるだけで、場面の移り変わりが視覚的に捉えやすくなるでしょう。
それでも理解が追いつかない時は、読み飛ばしていた注釈に立ち返ってください。
語句の意味だけでなく、物語の背景となる官位や当時の風習が説明されていることも少なくありません。
こうした小さな情報を一つずつ丁寧に繋ぎ合わせることで、混乱した状況を打開する突破口が見つかるのです。
まとめ:共通テスト古文で満点を!今日から変わる裏技的勉強法
今回は、共通テストの古文で高得点を目指している方に向けて、- 満点を狙うための思考法- 時間内に解き終えるためのテクニック- 知っているだけで差がつく裏技的な解法上記について、解説してきました。
共通テストの古文で高得点を取るためには、単語や文法の知識だけでなく、効率的な解き方を身につけることが非常に重要です。
限られた試験時間の中で正解を導き出すには、戦略的なアプローチが欠かせないからでした。
今、点数が伸び悩んで不安に感じている方もいるかもしれません。
しかし、心配する必要はありません。
この記事で紹介した方法を一つでも試してみることで、きっと点数に変化が現れるでしょう。
これまで積み重ねてきた学習は、決して無駄にはならないのです。
その努力に今回紹介した「裏技」という新たな武器を加えることで、古文への苦手意識が自信へと変わるはず。
まずは本文を読む前に設問に目を通すなど、すぐに実践できることから始めてみましょう。
筆者はあなたの挑戦を心から応援しています。