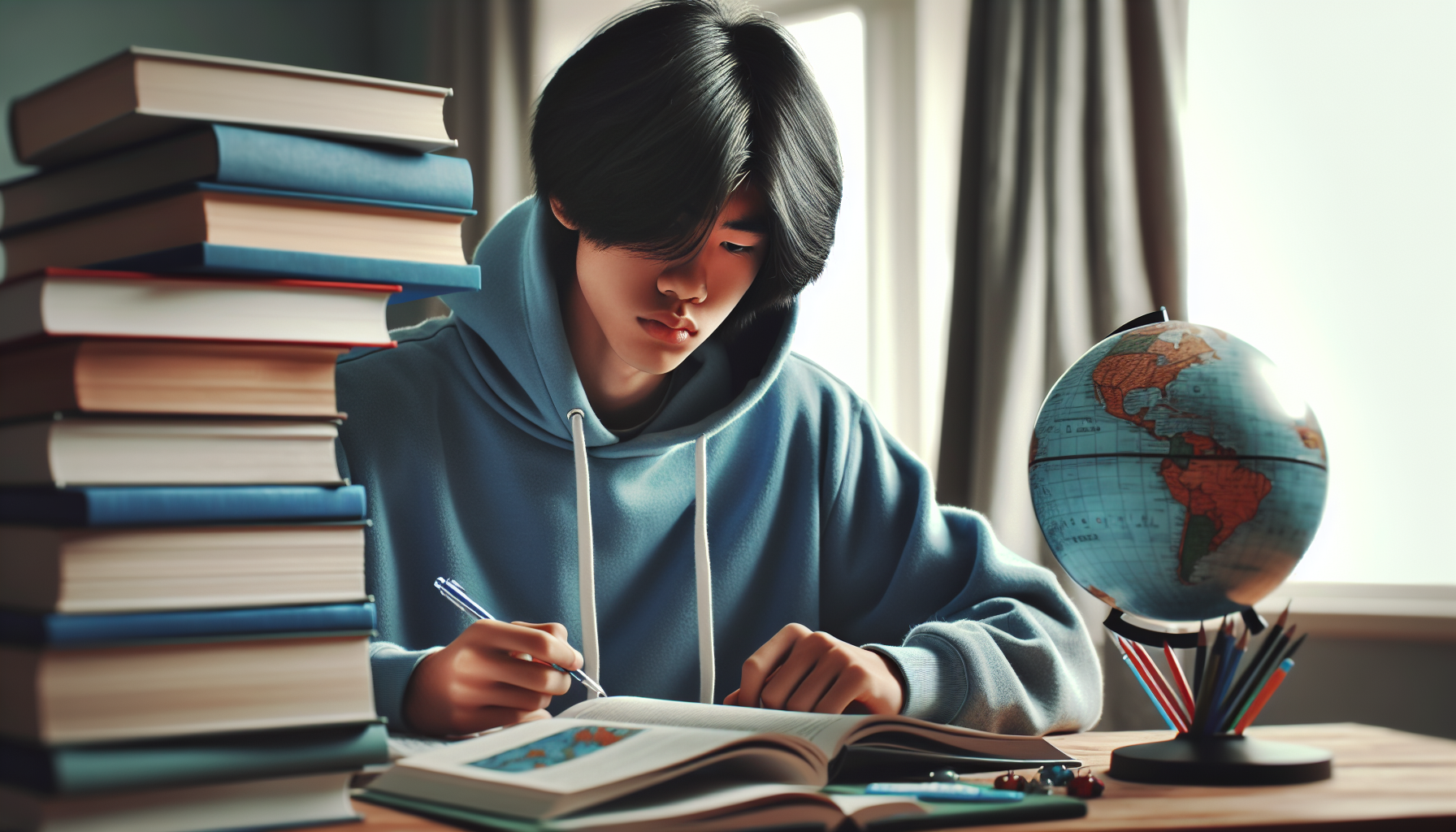共通テストの地理対策を進める中で、「勉強してもなかなか点数が上がらないけど大丈夫かな…」と不安を感じている方もいるでしょう。
あるいは、「暗記だけでは太刀打ちできない問題が多くて、どう対策すればいいかわからない…」と悩んでいるかもしれません。
しかし、地理には知識だけでなく、問題の解き方にもコツが存在します。
少し視点を変えるだけで、今まで解けなかった問題がスムーズに解けるようになることも珍しくありません。
諦めてしまう前に、得点に直結するテクニックを試してみてはいかがでしょうか。
この記事では、共通テストの地理で効率よく得点を伸ばしたいと考えている方に向けて、
– 時間をかけずに正解を導く問題の読み解き方
– 暗記に頼らず資料や統計から答えを推測するコツ
– 紛らわしい選択肢を素早く見抜く裏ワザ
上記について、解説しています。
今回ご紹介するのは、すぐに実践できる簡単なテクニックばかりです。
地理が苦手な方でも、きっと新たな発見があるはずでしょう。
この記事を読んで、自信を持って共通テストに臨むためのヒントを見つけてください。
共通テスト地理の裏ワザ:資料活用法
共通テスト地理で高得点を狙う秘訣は、問題に付随する地図や統計表などの「資料」を最大限に活用することです。
地理は暗記科目だと思われがちですが、実は答えのヒントの多くが資料の中に隠されています。
知識が少し曖昧な場合でも、資料を丁寧に読み解く力さえあれば、正解を導き出せる問題は少なくありません。
なぜなら、共通テストは単なる知識量を問うだけでなく、与えられた情報から地理的な事象を考察する思考力を試しているからです。
必死に覚えた地名や生産量の順位が直接役立つ場面は意外と少なく、むしろ初見の資料から何を読み取れるかが勝負の分かれ目となります。
出題者の意図を汲み取り、資料と対話する意識を持つことが重要でしょう。
具体的には、2つの都市の雨温図を比較する問題を考えてみましょう。
「ケッペンの気候区分」を完璧に暗記していなくても、最寒月気温や降水量のパターンを比べるだけで、大陸性気候か海洋性気候かといった特徴を推測できます。
このように、目の前の資料に集中し、その中に隠された情報を引き出す練習こそが、最高の得点アップ術なのです。
地図やグラフを使いこなすコツ
共通テスト地理で高得点を狙うには、地図や統計グラフの読解力が不可欠といえます。
地図問題でまず実践したいのは、縮尺と方位を必ず確認する習慣です。
この一手間が、思い込みによる致命的なミスを防ぎます。
特に地形図では、等高線の間隔に注目してください。
間隔が狭ければ急斜面、広ければ緩斜面という基本を意識するだけで、地形の読み取り精度は格段に向上するでしょう。
一方、グラフ問題では縦軸と横軸の単位を最初に確認することが肝心です。
「%」なのか「千人」なのかで、解釈は全く変わってきます。
例えば、日本の貿易相手国の変遷を示すグラフと、主要な貿易品目の推移を示すグラフを関連付けて考察するなど、複数の資料から情報を統合する訓練が得点アップへの近道となるのです。
資料集の効果的な使い方
資料集を単なる参考書と侮るのは非常にもったいない。
実は、共通テスト地理の得点力を飛躍させる「情報の宝庫」といえるでしょう。
効果的な使い方の秘訣は、地図と統計データを常にセットで確認する習慣をつけること。
例えば、二宮書店の「データブック オブ・ザ・ワールド」でカカオの生産上位国を見つけたら、すかさず地図帳でコートジボワールやガーナの位置、そして熱帯雨林気候区であることを確認します。
この一手間が知識を強固に結びつけ、応用問題への対応力を高めるのです。
また、教科書では白黒の図も、資料集のカラー写真を見れば一目瞭然。
カルスト地形やフィヨルドといった複雑な地形も、鮮明な写真とセットで覚えることで記憶に定着しやすくなります。
問題演習後は必ず関連ページを開き、自分だけの「弱点克服バイブル」としてカスタマイズしていくのが得点アップの裏ワザです。
問題演習で得点力を高める方法
共通テストの地理で安定して高得点を取るためには、問題演習の「質」を最大限に高めることが不可欠です。
ただ量をこなすのではなく、一問一問から多くの学びを得る意識を持つことで、応用力が飛躍的に向上するでしょう。
解きっぱなしにしない丁寧な演習こそ、得点力アップへの一番の近道といえます。
なぜなら、共通テストの地理は単なる知識の暗記だけでは太刀打ちできない問題が非常に多いからです。
統計資料や地図の読解、そして複数の情報を組み合わせて考察する思考力が問われます。
そのため、間違えた原因を深く分析し、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明できるレベルまで理解を深める作業が、本番での対応力を養う上でとても重要になります。
具体的には、過去問を解いた後、間違えた問題の解説を読むだけで終わらせないでください。
例えば、気候区分の問題で間違えたなら、該当地域の雨温図だけでなく、地図帳でその地域の農業や文化まで確認してみましょう。
また、正解の選択肢だけでなく、不正解の選択肢がなぜ誤りなのかを根拠立てて説明する習慣をつけることも、知識の定着に大きく貢献します。
過去問を使ったパターン学習
共通テスト地理の得点力を上げるには、過去問のパターン分析が極めて有効になります。
単に問題を解いて丸付けするだけでは、思考力はなかなか身につきません。
効果的な学習法は、気候や農業、工業といったテーマごとに過去5年から10年分の問題を一気に解くこと。
これにより、同じ統計グラフや地図が形を変えて何度も使われていることや、問い方の定番パターンが見えてくるでしょう。
特に重要なのが、選択肢の吟味。
なぜその選択肢が正解で、他の3つが間違いなのかを根拠を持って説明できるまで分析するのです。
誤った選択肢が作られる法則を把握すれば、本番での迷いが減り、確実な得点源となります。
また、過去問で扱われた統計は、『データブック オブ・ザ・ワールド』などで最新の数値を確認し、知識を更新しておくことも忘れないでください。
模試を活用した実戦力アップ
河合塾や駿台などが実施する共通テスト模試は、単なる実力測定の場ではありません。
本番で実力を最大限に発揮するための、最高のシミュレーションの機会になるのです。
まず意識すべきは、60分という試験時間内に全問を解き切るための時間配分の練習でしょう。
大問ごとの時間のかけ方や、迷った問題を一度飛ばす判断力など、自分なりのペースを確立してください。
そして最も重要なのが、模試後の徹底的な復習です。
結果に一喜一憂するのではなく、なぜその問題を間違えたのかを深く分析しましょう。
知識不足なのか、資料の読み取りミスなのか、原因を特定することが弱点克服の第一歩となります。
この分析結果を基に、残りの学習計画を修正していくことこそ、得点力を飛躍させる実践的なテクニックです。
地誌対策のポイント:出題傾向を読む
地誌問題を得点源にするには、全ての国や地域を網羅的に学習するのではなく、出題されやすい国やテーマに絞って対策することが最も効果的です。
やみくもに知識を詰め込もうとすると、膨大な情報量に圧倒されてしまい、かえって非効率になることも少なくありません。
共通テストでは、G7やBRICSなどの主要国、そして東南アジアやアフリカの特定の国に関する問題が繰り返し出題される傾向にあるのです。
なぜなら、共通テストの作成者は、現代世界を理解する上で重要となる国や、地理的な事象が典型的に見られる地域を問題として取り上げたいと考えているからです。
そのため、毎年同じような国やテーマが、少し視点を変えて問われることが多くなりました。
この「出題者の意図」を読み解くことが、地誌対策を有利に進めるための鍵となるでしょう。
具体的には、過去問を分析すると、アメリカの農業や工業、中国の経済発展、インドのIT産業といったテーマは頻出です。
また、ブラジルのコーヒー栽培やマレーシアの天然ゴム生産のように、特定の農産物や資源と国を結びつけて覚えることも重要になります。
このように、よく出る国や地域の特徴を系統地理の知識と関連させながら整理することで、効率的に得点力を高めることが可能なのです。
過去の出題地域を確認する
共通テスト地理の地誌問題で効率的に得点を伸ばすには、過去の出題傾向を把握することが不可欠です。
実は、試験で取り上げられる地域には一定の偏りが見られます。
例えば、東南アジア、西アジア、ヨーロッパ、アフリカ、ラテンアメリカといった地域は、繰り返し出題される頻出エリアといえるでしょう。
実際に2023年度の地理B本試験では、第4問で西アジア・北アフリカ、第5問で南アメリカがテーマとなりました。
まずは過去10年分程度の過去問を分析し、どの地域がどのようなテーマ(農業、工業、民族、宗教など)で問われたのかをリストアップしてみることをお勧めします。
この作業によって、出題頻度が高いにもかかわらず自分の理解が浅い地域が明確になるはずです。
重点的に対策すべき地域が見えたら、地図帳や資料集を使い、その地域の地形や気候、産業、歴史的背景などを関連付けて復習していく学習法が、得点力アップの最短ルートとなります。
新しい地域への備え方
過去問でカバーされていない地域への対策として、時事ニュースのチェックが極めて有効です。
G20やAPECといった国際会議の開催国や、大規模な自然災害があった地域は出題の有力候補になり得ます。
例えば、2023年に大地震に見舞われたトルコ周辺のプレート境界などは、知識として整理しておくと良いでしょう。
未知の地域が出ても慌てる必要はありません。
気候や地形、産業といった系統地理の知識を応用すれば、選択肢は十分に絞り込めます。
赤道直下の標高2,000mを超える都市なら、常春の気候(Cw)を推測できるはずです。
日頃から『データブック オブ・ザ・ワールド』などの資料集と地図帳を照らし合わせ、「なぜ」を考える習慣をつけましょう。
この思考訓練こそが、初見の地域に対する最大の武器となるのです。
共通テスト地理に関するよくある質問
共通テスト地理の学習を進める中で、「この勉強法で本当に大丈夫かな?」と不安に感じる方もいるでしょう。
ここでは、多くの受験生から寄せられる質問とその回答をまとめました。
あなたの抱える疑問をスッキリ解消し、自信を持って学習に取り組むためのヒントがきっと見つかるはずです。
試験が近づくにつれて、細かい疑問や他の受験生の進捗が気になってしまうのは自然なことでした。
しかし、そうした不安や疑問を放置してしまうと、学習の妨げになることも少なくありません。
疑問点を一つひとつクリアにしていくことが、精神的な安定と本番での得点力アップにつながるのです。
具体的には、「統計データはいつのものを、どこまで暗記すべき?」といった学習範囲の悩みや、「過去問や予想問題集は何年分解くのがベスト?」という演習量に関する質問を取り上げました。
さらに、「苦手な地形図問題を克服するコツ」や「試験当日の時間配分」といった、より実践的なテクニックについても詳しく回答していきます。
共通テスト地理の勉強時間はどれくらい必要?
共通テスト地理の勉強時間は、現在の学力や目標点によって大きく異なるため、一概に「何時間必要」とは断言できません。
一つの目安として、学校の授業とは別に150時間から200時間程度の学習時間を確保することが望ましいでしょう。
例えば、毎日1時間勉強するなら約5ヶ月から半年かかる計算になります。
もちろん、これはあくまで平均的な数値でしかありません。
もし目標点が6割程度であれば、基礎的な知識と資料の読み取り練習で100時間ほどで到達できる可能性はあります。
しかし、9割以上の高得点を狙うのであれば、細かい地誌の暗記や過去問を最低10年分は解くなど、プラスで100時間以上の演習が必要になるでしょう。
大切なのは総時間数よりも、自分の目標に合わせて計画的に学習を進めていくことなのです。
苦手な地理を克服するための勉強法
地理が苦手だと感じる多くの受験生は、地名や特産品の暗記に追われているのではないでしょうか。
共通テストの地理で求められるのは、単なる暗記力ではなく、物事の背景を理解する思考力です。
まず、手元に常に地図帳を置いて、学習中に登場した地名や地形をすぐに確認する習慣をつけましょう。
例えば、ブラジルのコーヒー生産について学んだら、サンパウロ州の場所を地図で見るだけで、記憶の定着率が格段に上がります。
また、日常生活と地理を結びつけてみるのも効果的でしょう。
スーパーで見るチリ産の鮭は、なぜ寒流のペルー海流が関係するのか、といった「なぜ?」を考える癖が思考力を養うのです。
最初から全範囲を網羅しようとせず、まずは気候区分や農業といった得意な分野を一つ作ることから始めると、苦手意識も薄れていきます。
このように、身近な事象から地理的な背景を探る学習法が、苦手克服への一番の近道となるでしょう。
まとめ:共通テスト地理はテクニックで驚くほど得点アップできる!
今回は、共通テストの地理であと一歩点数を伸ばしたいと考えている方に向けて、- 覚えておきたい出題傾向と対策- 知るだけで差がつく得点アップのテクニック- 本番で実力を発揮するための時間配分術上記について、解説してきました。
共通テストの地理は、知識の暗記だけで高得点を狙うのが難しい科目です。
なぜなら、統計資料や地図から情報を正確に読み解く力が問われる問題が、数多く出題されるからでした。
思うように点数が伸びず、焦りを感じている方もいるでしょう。
しかし、落ち込む必要は全くありません。
この記事で紹介したテクニックは、特別な知識がなくてもすぐに実践できるものばかりです。
まずは一つでも良いので、普段の学習に取り入れてみましょう。
これまで一生懸命に積み重ねてきた知識や学習時間は、決して無駄にはなりません。
その土台があるからこそ、今回お伝えした視点やテクニックがあなたの大きな力になるのです。
ものの見方を少し変えるだけで、今まで解けなかった問題が驚くほど簡単に感じられるかもしれません。
地理があなたの得点源になる日も、きっと近いでしょう。
さっそく過去問や問題集を開いて、今日学んだテクニックを試してみてください。
筆者は努力が実を結び、本番で最高の結果を出せることを心から応援しています。