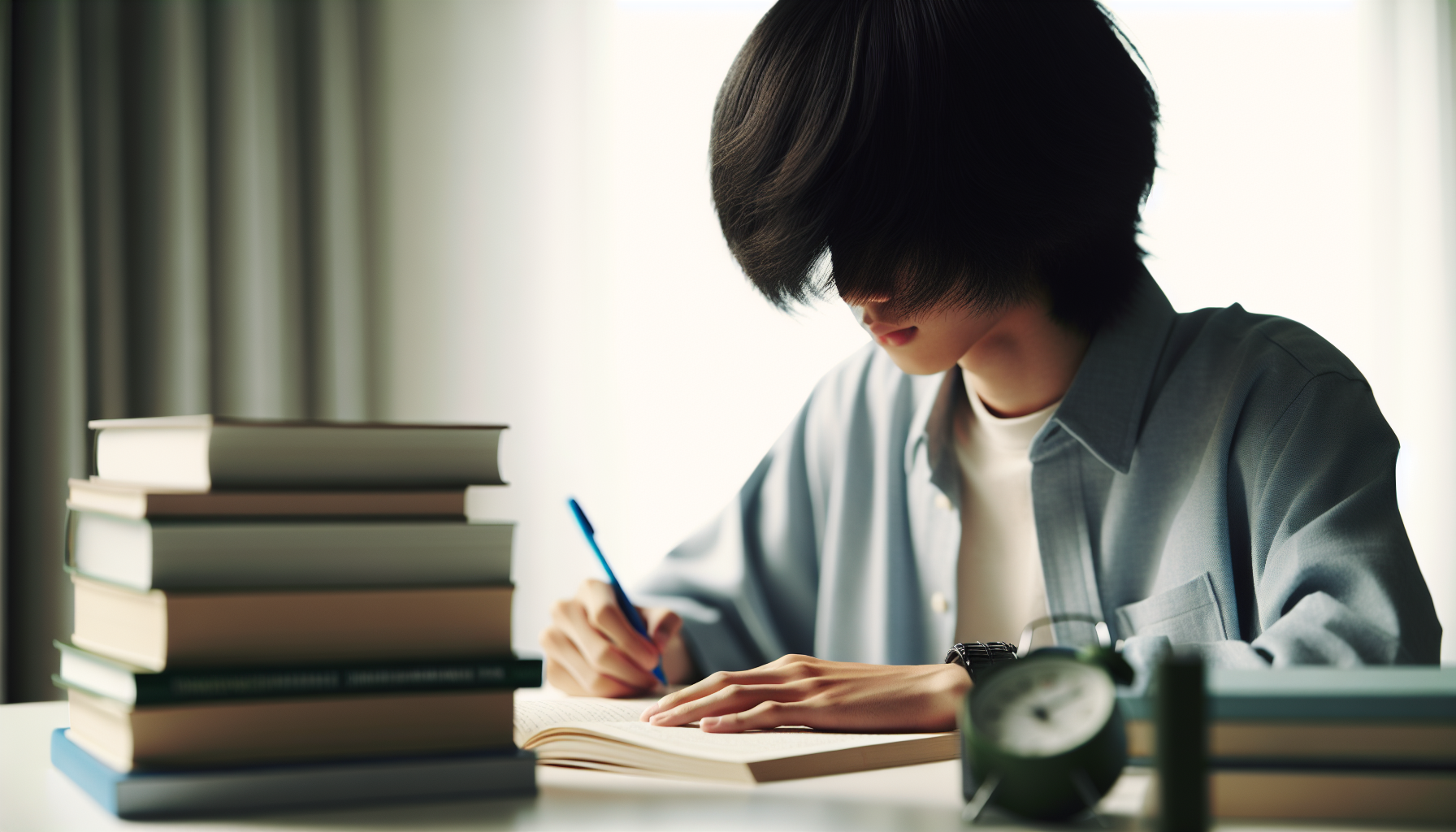共通テストの現代文で、「時間が足りなくて最後まで解ききれないけど大丈夫かな…」と焦ったり、「本文はなんとなく読めているのに、選択肢でいつも間違えてしまう…」と悩んだりしている方もいるのではないでしょうか。
思うように点数が伸びず、不安を感じることもあるかもしれません。
しかし、諦めるのはまだ早いです。
実は、現代文には点数に直結する効果的な解き方のコツ、いわゆる「裏ワザ」が存在するのです。
この記事では、共通テストの現代文で思うように点数が取れず、何か突破口を探している方に向けて、
– 時間内に問題を解き切るためのテクニック
– 紛らわしい選択肢を瞬時に見抜く秘訣
– 文章の要点を素早くつかむ読解術
上記について、解説しています。
現代文はセンスが必要だと思われがちですが、決してそんなことはありません。
正しい解き方と考え方を身につければ、誰でも安定して高得点を狙えるようになります。
この記事で紹介する裏ワザをあなたの勉強に取り入れて、本番での得点アップを目指しましょう。
ぜひ参考にしてください。
共通テスト現代文の裏ワザとは?
共通テスト現代文における「裏ワザ」とは、決して怪しいテクニックではありません。
出題の意図や問題形式の傾向を理解し、最短ルートで正解にたどり着くための合理的な思考法や着眼点のことです。
時間との勝負になりがちな現代文で、少し視点を変えるだけで驚くほどスムーズに解答できるようになるでしょう。
なぜなら、共通テストの現代文は、本文に書かれた客観的な事実や論理関係を正確に読み解く力を試す試験だからでした。
多くの受験生が時間不足に陥ったり、紛らわしい選択肢に惑わされたりするのは、文章のどこに注目して読めばよいか分かっていないことが原因かもしれません。
そのため、出題者が求める読解のポイントを知っているかどうかが、得点を大きく左右するのです。
具体的には、評論であれば「しかし」のような逆接の接続詞の後に筆者の主張が現れやすい点や、小説であれば登場人物の心情が大きく動く場面に注目するといった方法が挙げられます。
本文を読む際にこうしたポイントを意識するだけで、設問を解くために必要な情報を効率的に見つけ出すことが可能になります。
模試制作者の視点から考えるポイント
模試の問題を作成する側から見ると、共通テスト現代文には明確な出題意図が存在します。
作問者は、本文中の対比構造や因果関係、筆者の主張といった重要な部分を基に設問を設計していくのです。
つまり、文章の中で「しかし」や「なぜなら」といった接続詞の前後や、繰り返し述べられているキーワードに注目すれば、どこが問われる可能性が高いか予測できるでしょう。
また、不正解の選択肢にも一定のパターンが見られます。
「本文に書かれていない」「言い過ぎている」「本文とは逆の内容」といった典型的なダミー選択肢が用意されているものです。
これらの特徴を知っておけば、消去法で正解を絞り込みやすくなります。
作問者がどのように受験生を迷わせようとしているのか、その仕掛けを見抜く視点を持つことが、点数アップにつながる一つの秘訣といえるかもしれません。
設問の選択肢から本文の大意を掴む方法
本文を読む前に設問と選択肢へ先に目を通すことは、時間短縮につながる有効な裏ワザです。
この一手間を加えるだけで、文章全体のテーマや筆者の主張したい方向性、話の展開をある程度予測できるようになるでしょう。
具体的な方法として、まず設問文を読み、何が問われているのかを正確に把握してください。
次に、全ての選択肢を比較検討し、繰り返し登場するキーワードや、明らかに内容が対立している箇所を見つけ出します。
これらの共通点や相違点が、本文の主題や対比構造を理解する上で極めて重要なヒントになるのです。
例えば、選択肢に「グローバル化」と「ローカル化」といった対立軸があれば、本文がその対比を中心に論じられていると推測できます。
このように、先に選択肢を分析して本文の骨子を掴むことで、読むべきポイントが明確になります。
闇雲に読み進めるのではなく、解答の根拠を探すという目的意識を持って本文と向き合えるため、読解の速度と精度が格段に向上するでしょう。
現代文の点数を上げるコツ
共通テストの現代文で点数を上げる最も確実なコツは、実は小手先のテクニックではありません。
文章の構造を正確に理解し、設問の意図を正しく読み解くという、読解の本質的な力を養うことが最も重要です。
一見、遠回りに感じるかもしれませんが、この基本的な姿勢こそが、安定して高得点を取るための最短ルートだと言えるでしょう。
なぜなら、共通テストは受験生の個性的な解釈を求めているのではなく、文章に書かれた客観的な情報をいかに正確に、そして素早く処理できるかを測る試験だからです。
多くの受験生が時間不足に陥ったり、紛らわしい選択肢に迷ったりするのは、文章の論理的な展開を追わずに、なんとなくの印象で読み進めてしまうことが原因の一つでした。
例えば、評論では「しかし」のような逆説の接続詞の後に筆者の主張が来ることが多く、小説では登場人物の心情が変化するきっかけとなる出来事やセリフが問題で問われやすい傾向にあります。
闇雲に読み進めるのではなく、文章のどこに重要な情報が書かれているのかを意識しながら読み解く練習を重ねることが、得点力アップに直結するのです。
速読で時間を有効活用する
共通テストの現代文では、限られた時間内に長文を読み解く必要があり、速読は非常に有効なスキルです。
すべての文章を同じペースで読むのではなく、強弱をつけることを意識してみましょう。
例えば、文章全体の流れを掴む段階では、接続詞や段落の冒頭・末尾の文章に注目し、速いスピードで読み進めるのが効果的でしょう。
一方で、設問で問われている箇所や、筆者の主張が述べられている重要な部分は、じっくりと時間をかけて精読する必要があります。
普段の学習から、時間を意識して問題演習に取り組むことが大切です。
タイマーを使って一文を読むスピードを計測したり、文章全体の構造を素早く把握する練習を繰り返したりすることで、本番でも焦らずに時間内で問題を解ききる力を養えます。
選択肢を効果的に絞り込むテクニック
共通テストの現代文で高得点を狙うには、選択肢を効率的に絞り込む技術が欠かせません。
最も基本的な方法は消去法です。
本文の内容と明らかに矛盾している選択肢や、全く言及されていない事柄を含む選択肢から除外していきましょう。
次に、残った選択肢を吟味します。
「~に過ぎない」といった限定的な表現や、「すべての」といった過度に一般化する言葉が含まれる選択肢は、誤りである可能性が高いと考えられます。
また、本文の一部の言葉を使いつつも、主語が入れ替わっていたり、因果関係が逆になっていたりする巧妙な引っかけも頻出するため注意が必要です。
紛らわしい選択肢が二つ残った場合は、両者を並べて比較し、どちらがより筆者の主張に沿っているかを慎重に判断してください。
これらのテクニックを過去問演習で繰り返し実践し、素早く正解を見抜く力を養うことが得点アップに繋がります。
共通テストのQ&A
共通テストの現代文に関して、「時間配分はどうすればいい?」「小説と評論、どっちから解くべき?」といった疑問を抱えている方もいるでしょう。
実は、こうした受験生特有の悩みは、試験のポイントをあらかじめ理解しておくだけで、本番で慌てることなく冷静に対処できるようになります。
なぜなら、多くの受験生がつまずく点は、出題形式や80分という制限時間など、共通テスト特有の要因に起因することが多いからです。
膨大な文章量と紛らわしい選択肢を前に、誰もが同じような壁にぶつかるのは当然のことと言えるでしょう。
だからこそ、頻出する疑問への対策を事前に立てておくことが、他の受験生と差をつける秘訣なのです。
具体的には、「本文のどこを根拠にすれば正解の選択肢を選べるのか」という読解の核心に迫る質問や、「過去問は何年分を解くべきか」といった学習計画に関する相談がよく寄せられます。
例えば時間配分であれば、大問1の評論に約40分、大問2の小説に約35分、残りを最終確認に充てるのが一つの目安です。
このように、疑問を一つひとつ解消していくことが、自信を持って本番に臨むための鍵となります。
よくある質問とその回答
共通テストの現代文に関して、受験生からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q. 評論と小説、どちらから解くのが有利ですか?A. 一般的には、論理構造が明確で客観的に読み解きやすい評論から手をつけるのがおすすめです。
しかし、物語の読解が得意で、小説の方がスムーズに解答できるのであれば、そちらを優先しても構いません。
過去問や模試を通じて、両方の順番を試してみて、自分にとって最も得点しやすいパターンを見つけておきましょう。
Q. 時間が足りなくなってしまいます。
どうすれば良いでしょうか?A. 共通テストの現代文は大問1問あたり20分が目安です。
特に小説問題は、登場人物に感情移入しすぎると時間を浪費しがちになります。
設問で何が問われているかを正確に把握し、本文の該当箇所を素早く見つけ出す練習を重ねることが時間短縮の鍵となります。
普段の学習から時間を計り、スピードを意識して取り組む習慣をつけてください。
Q. 選択肢を2つまで絞れるのですが、最後で間違えてしまいます。
A. 最終的な2択で迷った際は、選択肢の表現を吟味することが大切です。
「~だけ」「必ず~」のような断定的な表現や、本文の内容を拡大解釈している選択肢は誤りである可能性が高いでしょう。
本文の記述を根拠に、最も客観的で適切な表現を選び出す視点を持ってください。
試験前に知っておきたい情報
共通テスト本番で実力を最大限に発揮するため、試験前に押さえておきたい情報があります。
まず、80分という試験時間では、大問1の評論に約35分、大問2の小説に約35分、残りの10分を見直しに充てるのが理想的な時間配分といえるでしょう。
当日の持ち物として、受験票やHBの黒鉛筆、プラスチック製の消しゴムは必須です。
加えて、秒針付きのアナログ時計を用意しておくと、時間管理がしやすくなります。
解答はマークシート方式のため、問題番号と解答欄のズレには細心の注意を払いましょう。
問題を解き終えるごとにマークするなど、自分なりのルールを決めておくとミスを防げます。
また、試験会場は暖房が効きすぎている場合もあるので、カーディガンなど着脱しやすい服装で温度調節できるように備えておくと安心です。
これらの準備を万全にして、落ち着いて試験に臨んでください。
関連情報と参考資料
共通テスト現代文の対策をさらに盤石にするためには、この記事で紹介した裏ワザに加え、信頼できる関連情報や参考資料を積極的に活用することが非常に重要です。
より深い知識を得たり、異なるアプローチを学んだりすることで、あなたの得点力はさらに向上するでしょう。
なぜなら、一つの情報源だけに頼るのではなく、複数の視点から学ぶことで思考の幅が広がり、どのような形式の問題にも対応できる真の読解力が身につくからです。
自分に合った教材や学習法を見つけることで、学習のモチベーション維持にもつながります。
具体的には、大学入試センターが公開している過去問題や出題趣旨を確認すると、作問者の意図を深く理解できます。
また、河合塾や駿台といった大手予備校が提供する詳細な分析データや、書店で評価の高い『きめる!共通テスト現代文』などの参考書を手に取ってみるのも有効な手段です。
これらの資料には、長年の分析に基づいた有益な情報が凝縮されています。
他の受験生の成功事例
実際に共通テストの現代文で高得点を獲得した先輩たちの多くは、独自の工夫を取り入れていました。
例えば、ある受験生は問題演習の際に、なぜその選択肢が不正解なのかを一つひとつ言語化して説明する練習を徹底したそうです。
この訓練により、選択肢の微妙な違いを見抜く力が養われ、本番では評論・小説ともに9割を超える得点を達成できました。
また、別の成功例として、先に設問と選択肢を読んでから本文を読むというアプローチで、解答時間を大幅に短縮したケースもあります。
本文を読む前に大まかな内容や問われるポイントを把握することで、効率的に解答の根拠を探せるようになったのです。
伸び悩んでいた時期からこの方法に変えたことで、模試の点数が安定して8割を超えるようになったという声は少なくありません。
参考書籍とオンラインリソース
共通テスト現代文の対策には、市販の参考書やオンラインリソースの活用が欠かせません。
書籍では、解答プロセスを丁寧に解説している『きめる!共通テスト現代文』が受験生の定番となっています。
また、評論や小説で頻出するキーワードの意味を深く理解するためには、『現代文キーワード読解』で語彙力を強化しておくと良いでしょう。
オンラインでは、まず大学入試センターの公式サイトで過去問を無料で入手できます。
実践演習には欠かせない資料なので、必ず確認してください。
さらに、映像授業も有効な学習手段となります。
「スタディサプリ」などのサービスでは、プロ講師による分かりやすい解説講義が視聴可能です。
YouTubeにも予備校講師が無料で公開している有益な動画が数多く存在します。
これらの教材を自分の学習スタイルに合わせて組み合わせ、効率的に得点力アップを目指しましょう。
共通テスト現代文の裏ワザに関するQ&A
共通テスト現代文の裏ワザについて、多くの受験生が抱える疑問や不安は似通っているものです。
ここでは、そうした典型的な質問にQ&A形式でお答えし、あなたの悩みをスッキリ解消していきます。
裏ワザは本当に効果があるのか、どんな問題形式で有効なのかといった疑問に、一つひとつ丁寧にお答えしましょう。
受験が近づくにつれて、「もっと効率的に点数を伸ばしたい」と焦りを感じるのは当然のことです。
特に現代文は対策が立てにくいと感じる方も多く、少しでも有利になるテクニックを知りたいと思うのは自然な心理でしょう。
よくある疑問を事前に解消しておくことで、迷いなく本番の試験に臨むことができ、それが自信にもつながります。
例えば、「選択肢の吟味だけで正解を導き出す裏ワザはありますか?」や「時間配分がうまくいかない時に使えるテクニックは?」といった質問は毎年多く寄せられます。
また、「評論と小説で、それぞれ有効な裏ワザは異なりますか?」という具体的な疑問を持つ方もいるかもしれません。
これらの実践的な問いに答えることで、あなたの得点力をさらに引き上げる手助けとなるはずです。
裏ワザを使う際の注意点
共通テスト現代文の裏ワザは、時間がない時や迷った時に役立つ可能性がありますが、その利用には注意が必要です。
最も大切なのは、裏ワザはあくまで補助的な手段であり、万能ではないと理解しておくことでしょう。
小手先のテクニックに頼りすぎると、かえって本文の内容を正確に読み取る力が疎かになる危険性があります。
例えば、消去法などのテクニックは有効ですが、それは本文の論理構成や筆者の主張を正しく理解していることが大前提です。
本文を読まずに選択肢の表現だけで判断しようとすると、巧妙な引っかけ問題に対応できず、失点につながりかねません。
裏ワザは、どうしても正解が絞り込めない時の最終手段と位置づけ、普段の学習では地道に読解力や語彙力を高めることに専念するのが、高得点への一番の近道だといえます。
試験対策の進め方に関する質問
共通テスト現代文の対策は、まず過去問や予想問題集を繰り返し解くことから始めましょう。
重要なのは、時間を計り、本番さながらの状況で演習を重ねることです。
大問1つあたり20分を目安に時間配分を体に染み込ませると、本番でも焦らずに済みます。
問題を解き終えたら、必ず答え合わせと丁寧な復習を行ってください。
なぜその選択肢が正解で、他の選択肢が間違いなのか、本文の根拠を明確に説明できるまで理解を深める作業が実力向上に直結します。
評論は論理構造を、小説は登場人物の心情や場面の変化を意識して読む練習を積むのが効果的です。
裏ワザ的なテクニックは、こうした地道な基礎演習を重ねた上で活用してこそ、真価を発揮するでしょう。
夏休み明け頃から本格的な演習を開始し、着実に実力をつけていくことをおすすめします。
まとめ:共通テスト現代文の壁を乗り越える最後の秘訣
今回は、共通テストの現代文で思うように点数が伸びず、悩んでいる方に向けて、- すぐに試せる点数アップの裏ワザ- 時間内に解き終えるための秘訣- 評論・小説それぞれの攻略法上記について、解説してきました。
共通テストの現代文は、ただ闇雲に文章を読むだけでは点数に結びつきにくいのが現実です。
なぜなら、解答の根拠は必ず本文中にあり、それを見つけ出すための着眼点や思考法が存在するからでした。
文章が難しくて内容を掴めなかったり、時間内に解き終わらなかったりして、焦りを感じている方もいるでしょう。
しかし、もう心配する必要はありません。
この記事で紹介した秘訣を一つでも実践することで、問題文や設問の見え方が大きく変わってくるはずです。
まずは、解きやすいと感じたものから試してみましょう。
これまで一生懸命に勉強してきた努力は、決して無駄にはなりません。
その積み重ねに、正しい解き方という武器が加わることで、実力は飛躍的に伸びていきます。
現代文が苦手科目から得意科目へと変わる日も、そう遠くはないでしょう。
確かな手応えを感じながら問題を解き進める自分を想像してみるのも良いかもしれません。
さあ、今日から過去問や問題集を使って、紹介した裏ワザを試してみてください。
筆者は、あなたが試験本番で最高の結果を出せることを心から応援しています。